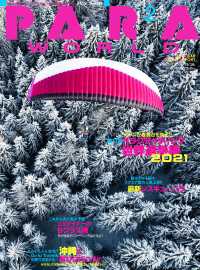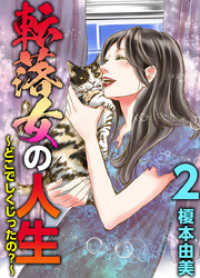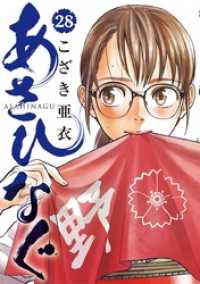内容説明
奥信濃地方に江戸時代から伝わる農書に遺された不思議な文字「ぢしんうらない」。この文字の意味を求めて『日本書紀』『続日本紀』の世界へ。そこには古代日本の権力中牲の争いと災害疫病の事実があった。
目次
古代日本が中央集権国家をあゆみ始めたころ
古代日本が律令国家を形づくり始めたころ
律令国家が完成するころ
天平七年・九年の天然痘大流行と藤原氏衰退
東大寺の完成と藤原仲麻呂の隆盛
律令制のゆらぎと朝廷の分裂
皇位が天武系から天智系に代わり藤原氏が復活
平安京遷都が進められていたころ
九世紀末の寒冷期
「摂政」「関白」が設置されるころ
藤原氏による政治権力の独占
著者等紹介
佐藤洋子[サトウヨウコ]
大気が汚染され、東京下町の環境が極度に悪かったころ、多数の個人出資による診療所に勤務。子育て時期は保育園が圧倒的に少なく、公立病院内保育所設立に参加。子どもの成長につれ、小学校区ごとに求められた地域の学童保育所の設立に参加、指導員として働く。国際児童年に、「子どもの心と体を考える会」を結成、地域で「子どもの体調べ」(日本体育大学正木健雄教授・横浜商科大学有志の協力)を年一回、十回実施。歴史遺産の地に大型宅造が計画されていたころ、逗子米軍住宅建設計画がもちあがり、逗子市スローガン「緑豊かな平和都市」に魅せられた逗子に住んだのに、それは困るという立場から活動に参加。平成初め頃、市の望ましい環境像を模索するためには現状を把握すべきということで設けられた「逗子市環境管理計画策定部会」(委員長・東京大学農学部教授武内和彦氏)に市民委員として参加(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。