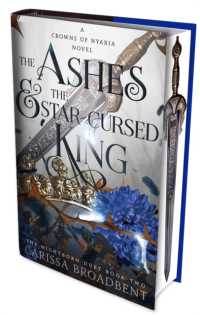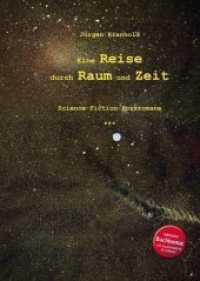内容説明
沖縄現代史研究のパイオニア、沖縄闘争の伴走者が、今、沖縄から安保の本質を問う。
目次
1 戦後の日米関係と沖縄(占領政策における日本・沖縄の位置づけ;構造的沖縄差別の上に確立された戦後の日米関係と復帰運動;安保改訂と構造的沖縄差別;沖縄返還と安保問題の局地化)
2 東西冷戦終焉後の沖縄の位置と民衆の闘い(一極支配を目指す米国・安保「再定義」と普天間問題の焦点化;政権交代の挫折と新局面を迎える沖縄の闘い)
3 中国の大国化・日米同盟の空洞化・東日本大震災(尖閣諸島(釣魚諸島)問題から何が見えてきたか
国境地域は辺境か平和創造の場か
東日本大震災をどうとらえるか?)
4 構造的沖縄差別克服の可能性をどこに見出すか(世論調査とメディアの論調から見る日米安保・沖縄;ヤマトからの介入、ヤマトとの連帯;国際的な広がりの中で)
著者等紹介
新崎盛暉[アラサキモリテル]
1936年、東京に生まれる。沖縄大学名誉教授、元学長。沖縄平和市民連絡会代表世話人。1960年代、東京都庁に勤務のかたわら「沖縄資料センター」の活動に従事。1974年、沖縄大学に赴任、大学再建に尽力。同時にさまざまな住民・市民運動に参加し、1982年、一坪反戦地主会を組織する。1993年、故岡本恵徳氏らと季刊『けーし風』を創刊(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
53
ちょうど民主党政権時代の普天間・辺野古のドタバタと尖閣諸島問題、3.11震災を踏まえた形での基地問題を整理する形で沖縄から見たヤマトの差別的扱いをえぐり出している。この著者の本はそれこそ学生時代から数多く読み、ご本人の話も2回直接うかがっている。基本的にブレのない論であり、また研究者らしい丁寧な資料解読もあるが、一方で煮えたぎるような熱い想いも感じさせる。意外だったのが鳩山由紀夫に対する比較的好意的な評価。一方当時の民主党政権、特に前原・北澤に対しては辛辣。でもこの方も亡くなって7年。あとを継ぐ者は?2025/04/27
Hiroki Nishizumi
1
残念ながら既知の事実とよくある論法だけで、新しい視点や提案はない感じだ。評価D2012/08/02
ふら〜
0
2012年の本なのでまだ翁長県政になる前。安保を見直すんだーという良くある話。しかし構造的沖縄差別という言葉を考えた人はキャッチコピーのセンスあるよね(同意するかは別問題として)2018/03/25