目次
1(石川啄木―熟成のパースペクチブ;啄木とペドクラシー―その生と詩と死とカミ;宮澤賢治―文語定型はありがたい ほか)
2(失語と断念―石原吉郎論)
3(呪縛の構造;詩は言い切るためにある;若き詩人へのパステルナークの手紙 ほか)
4(“ジーズニ”―この重い言葉;文学における「連想」―外国文学の理解とは何か;二葉亭四迷・その短命な訳業 ほか)
5(ソ連展望―フルシチョフ路線背後の力;創作・石の家にて)
著者等紹介
内村剛介[ウチムラゴウスケ]
評論家、ロシア文学者。1920年。1934年、渡満。1943年、満洲国立大学哈爾濱学院を卒業。同年、関東軍に徴用され、敗戦とともにソ連に抑留される。以後、11年間をソ連内の監獄・ラーゲリで過ごし、1956年末、最後の帰還船で帰国する。帰国後、商社に勤務する傍ら文筆活動を精力的に展開し、わが国の論壇、ロシア文学界に大きな影響を与える。1973年から78年まで北海道大学教授、1978年から90年まで上智大学教授などを勤める。2009年1月死去(享年88)
陶山幾朗[スヤマイクロウ]
1940年、愛知県生まれ。1965年、早稲田大学第一文学部を卒業。現在、雑誌『VAV(ばぶ)』主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
-

- 和書
- 人口減少社会の未来学
-
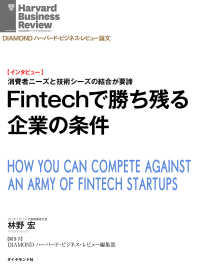
- 電子書籍
- Fintechで勝ち残る企業の条件(イ…







