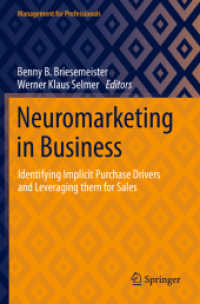目次
第1章 第二言語習得(SLA)研究の意義(学習者が習得すべき言語能力とは?;言語を使うとはどういうことか?;言語習得過程では何が起きているのか? ほか)
第2章 外国語の定着を阻む要因(学習者の習得過程はみな同じか?;学習者の言語は右肩上がりに発達するか?;母語はどれほど干渉するのか? ほか)
第3章 教室で教師ができること(教室でやるべきは、まず文法か?;文法説明は必要か?;インプットは十分に与えられているか? ほか)
著者等紹介
小柳かおる[コヤナギカオル]
福岡県出身。ジョージタウン大学にて博士号(言語学)取得。(社)国際日本語普及協会(AJALT)、アメリカ国際経営大学院、ジョージタウン大学等の日本語講師。上智大学比較文化学部(現・国際教養学部)助教授などを経て、上智大学言語教育研究センター/大学院言語科学研究科教授。2018年9月から2019年8月まで、フランス国立東洋言語文化大学(INALCO)日本学研究センター特別招聘研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hiroh
16
インプットの大切さ。意味交渉が必要。音と文字、意味が結びつくことが大切。「気づき」とは、この文法が使われているんだ!でなくてもいい、そこに注目することでいい。協働の大切さ。語学を教える、学ぶ人は第二言語習得の知識は必須だと思う。2022/03/10
アンゴ
2
★★★★★ 従来の日本語教育の在り方を真向から否定する結論を非常に控えめな表現を使って具体的に説く。 外国語を学習する第二言語習得とは何かの第一章、外国語習得の障害についての第二章、現場の教師がとれる具体的アクションの第三章の構成。 直接的な批判をしていないが、現状の日本の日本語学校や養成講座の教授法では、言語運用能力を伴う習得に結び付かないと論理的根拠を示し明確に示唆している。 『認知的アプローチから見た第二言語習得』を先に読んでいたので論理的背景や根拠がかなり割愛されていても良く理解できた。2023/02/06
パンケーキ
1
読みやすかったです。これを含む他の類書をローテーションして読んで知識を強化していきたい。2022/10/31
-

- 和書
- 茶の湯ドリル