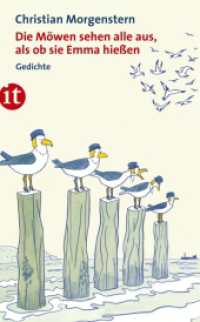出版社内容情報
日本語の雑談を分析、その構造(連鎖組織)や言語形式を明らかにし、これまで行われてこなかった雑談の体系化を試みる。また、雑談をどのように日本語教育などにおける会話の指導に活かすことができるかについても論じる。
本研究は、日本語の会話教育において、雑談を体系的に指導することができるようにするため、日本語の雑談を分析し、その構造を明らかにしようとするものである。(中略)筆者が日本語の雑談を研究対象とするに至ったのは、複数の留学生から「日本人の会話に入っていけない」「日本人の友達がなかなかできない」という悩みを打ち明けられたことによる。彼らはみな、来日後、日本語学校に通って日本語能力試験の1級に合格し、日本での生活経験が数年あり、日常生活で日本語に困ることはほとんどないと思われるレベルの日本語の運用能力を有する大学生であった。また、留学生以外にも、「子供を持つ外国人の主婦の人が、公園での日本人のお母さんたちの会話に入っていけなくて悩んでいる」といった話を聞いたり、地域の日本語ボランティアの方から、「日本人と結婚した外国人の方に、家族や近所の人との会話を教えるにはどうしたらいいか」という質問を受けたりする機会もあり、これらの経験を通して、雑談は、日常生活の中で簡単に自然習得できるものではなく、体系的に指導しなければならない重要な項目なのではないかと考えるようになった。 (はじめに)
第1章 日本語の会話教育に関わる先行研究
1.1 日本語の話しことばに関する研究
1.2 会話教育の指導項目に関する研究
1.3 雑談の教育における指導項目のあり方
第2章 雑談の分析方法
2.1 研究の目的
2.2 分析に用いる概念
2.3 分析データの概要
2.4 分析方法
第3章 雑談の連鎖組織の類型
3.1 話題内容の種類による連鎖組織の分類
3.2 第一発話のタイプによる連鎖組織の分類
3.3 話題内容と第一発話のタイプによる連鎖組織の類型化
3.4 各連鎖組織に現れる言語形式の抽出
3.5 本研究の分析から得られた連鎖組織の類型ごとの一覧
第4章 会話参加者に関することを話題とする連鎖組織
4.1 質問から始まる連鎖組織
4.2 報告から始まる連鎖組織
4.3 共有から始まる連鎖組織
4.4 独り言から始まる連鎖組織
4.5 会話参加者に関することを話題とする連鎖組織のまとめ
第5章 第三者に関することを話題とする連鎖組織
5.1 質問から始まる事態・属性系の連鎖組織
5.2 報告から始まる事態・属性系の連鎖組織
5.3 第三者に関することを話題とする連鎖組織のまとめ
第6章 現場の事物に関することを話題とする連鎖組織
6.1 相手に属するものを話題とする場合の連鎖組織
6.2 現場の事物を話題とする際の言語形式上の特徴
6.3 現場の事物に関することを話題とする連鎖組織のまとめ
第7章 雑談の体系的な教育に向けて
7.1 話題開始の発話タイプによる話題内容の性質の違い
7.2 雑談の教育の体系化への考察
7.3 雑談の対照研究の重要性
第8章 おわりに
8.1 本研究のまとめ
8.2 残された課題
【著者紹介】
筒井佐代(つつい さよ) 大阪大学言語文化研究科准教授
岡山県生まれ。愛知県立大学外国語学部講師、大阪外国語大学外国語学部助教授、アメリカ合衆国ミネソタ大学客員研究員、大阪大学世界言語研究センター准教授を経て、現職。研究分野は、日本語教育学、会話分析。共著に『日本語文型辞典』(くろしお出版)。
内容説明
本研究は、日本語の会話教育において、雑談を体系的に指導することができるようにするため、日本語の雑談を分析し、その構造を明らかにしようとするものである。
目次
第1章 日本語の会話教育に関わる先行研究
第2章 雑談の分析方法
第3章 雑談の連鎖組織の類型
第4章 会話参加者に関することを話題とする連鎖組織
第5章 第三者に関することを話題とする連鎖組織
第6章 現場の事物に関することを話題とする連鎖組織
第7章 雑談の体系的な教育に向けて
第8章 おわりに
著者等紹介
筒井佐代[ツツイサヨ]
大阪大学言語文化研究科准教授。岡山県生まれ。愛知県立大学外国語学部講師、大阪外国語大学外国語学部助教授、アメリカ合衆国ミネソタ大学客員研究員、大阪大学世界言語研究センター准教授を経て、現職。研究分野は、日本語教育学、会話分析(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。