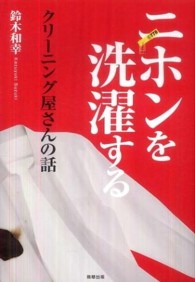出版社内容情報
教師と学生が対話やプロセスを重視しともに評価しあい、教室内だけなく社会とも積極的に関わっていくこと(=「アセスメント」という考え方)が、教師と学生の成長にいかに重要であるか。その理論と実践を収めた好著。
学習者に対する評価は、イコール、テストの結果ではない。教師と学習者がともに評価しあい、教室内だけなく社会とも積極的に関わっていく「アセスメント」という考え方の、理論(3篇)およびその具体的な実践例(6篇)を収録。教師と学習者ないし学習者同士の対話、結果ではなくプロセスを重視することが、教師と学習者にいかに好影響を与えるかという貴重な事例など、刺激的な示唆を数多く含む。
第1章 アセスメントの歴史と最近の動向:
社会文化的アプローチの視点を取り入れたアセスメント
佐藤 慎司・熊谷 由理
第2章 CEFRにおける評価とアセスメント
真嶋 潤子
第3章 語用論的能力の諸相とアセスメント:
敬語評価の問題点
渡辺 素和子/パトリシア・ウェッツェル
第4章 ピアラーニングとアセスメント:
ブログを用いたピアラーニング
ナズキアン 富美子
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
isao_key
5
この本での「アセスメント」とは「評価」に代わる用語として「教師が教室内で用いている評価など、学習者のパフォーマンス、達成を評価する様々な方法」という意味で使っている。本書はアセスメントについての理論編と十実践編からなっている。中に興味深い活動事例が多く載せられている。例えば学習者が日常生活について日本語でブログを書いて、それについて他の学習者がメッセージを送る。後日クラスで各学生のブログについて学習者間で5段階の評価をしコメントを出しあう。客観的な意見を出すことで自身の学習にもフィードバックされる。2013/02/19