出版社内容情報
SLA研究のためのノウハウを網羅したコンパクトな入門書。研究のためのアイデア、目的・仮説の設定、データ収集方法の模索、研究計画をいかに作成し、実行に移して、データを収集・分析し、学会報告にどのようにまとめるかを紹介。
筆者はこれまで、第二言語におけるリーディング、メンタルレキシコン、シャドーイングや音読を活用した学習法の効果について、心理言語学や認知科学の観点から検証してきました。言い換えると、第二言語習得の前提となる研究分野、つまり人が外界からのインプット情報をいかに知覚・処理し、そして記憶に蓄えるかということに関する成果を積極的に活用した第二言語習得研究を行ってきました。本書はささやかながら、その研究のためのノウハウを提示し、SLA研究への平易でコンパクトな入門書を目指したものです。とりわけ、飛躍的な進歩を遂げつつある、認知的な観点からの量的SLA研究に焦点をあわせました。(著者:「はじめに」より)
はじめに:SLA研究は面白い!
Step 1 SLA研究とはどんな学問か
1.1 第二言語とは?習得とは?
1.2 近年のSLA研究興隆の理由
1.3 SLA研究の種類:仮説検証型と仮説探索型
1.4 本書の趣旨と対象とする研究のタイプ
ここで問題です
Step 2 先行文献をいかに読んでテーマを設定するか
2.1 文献はどのようにして集める?
2.2 文献はどのようにして読む?
2.3 研究テーマの設定方法は?
ここで問題です
Step 3 リサーチプランをいかに作成するか
3.1 リサーチプランの構成は?
3.2 研究の背景はどう書く?
3.3 研究の目的・検討課題・仮説はどう書く?
3.4 研究方法はどう書く?
3.5 リサーチプランってこんなもの:サンプルは?
ここで問題です
Step 4 心理言語学的SLA研究データにはどのようなものがあるか
4.1 正答数データ
4.2 プロトコルデータ
4.3 反応時間データ
4.4 音声分析データ
4.5 眼球運動データ
4.6 脳科学データ
4.7 コーパスデータ
ここで問題です
Step 5 実験実施とデータ集計をどのようにして行うか
5.1 被験者をいかに集めるか
5.2 実験実施上の留意点
5.3 データ集計の実際
ここで問題です
Step 6 学会発表をどのようにして行うか
6.1 結果から結論・考察をいかに導くか
6.2 発表学会・研究会を選ぶ
6.3 発表プロポーザルを書く
6.4 学会発表のノウハウ
ここで問題です
Step 7 第二言語習得研究の目的は
7.1 文献紹介:統計処理、論文の書き方、研究法、用語辞典
7.2 第二言語習得研究に必要な資質
7.3 第二言語習得研究の究極の目的
ここで問題です
【著者紹介】
関西学院大学・大学院教授〈博士(応用言語学)〉
専門は心理言語学、応用言語学。 現在は、ことばの科学研究会(JSSS)、大学英語教育学会(JACET)リーディング研究会、外国語教育メディア学会(LET)関西支部基礎理論研究部会の3つを中心に活動。
主な著書:『英語リーディングの認知メカニズム』(共編著:くろしお出版)、『英語の書きことばと話ことばはいかに関係しているか』(2002年大学英語教育学会学術賞)(くろしお出版)、『英語のメンタルレキシコン:語彙の獲得・処理・学習』(編著:松柏社)、『応用言語学事典』(共著:研究社)、『決定版 英語シャドーイング』(共著:コスモピア)、『決定版 英語エッセイ・ライティング』(監修・共著:コスモピア)、『第二言語理解の認知メカニズム』(単著:くろしお出版)、『日本人英語学習者の英単語親密度・文字編』(共著:くろしお出版)、『英語語彙指導ハンドブック』(共編著:大修館書店) 、『シャドーイングと音読の科学』(単著:コスモピア)、『ことばと認知のしくみ』(共編著:三省堂)、『シャドーイングと音読:英語トレーニング』(監修・共著:コスモピア)、『日本人英語学習者の英単語親密度・音声編』(共著:くろしお出版)、『リーディングとライティングの理論と実践:英語を主体的に「読む」・「書く」 (英語教育学大系第10巻) (共著:大修館書店)、『英語リーディング指導ハンドブック』(共編著:大修館書店)など。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
isao_key
栗山 陸
Yoshika
-
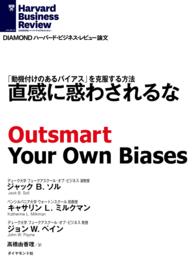
- 電子書籍
- 直感に惑わされるな DIAMOND ハ…




