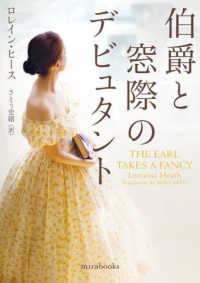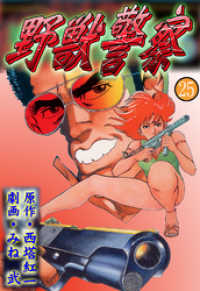出版社内容情報
国際化に伴い日本でもその数が急増している「移動」する(国境を越えて育つ・複数の言語の中で育つ)子どもたち。現在各方面で活躍する「移動する子ども」だった大人達が、自身の心の軌跡を惜しみなく語る対談集。
国際化に伴い日本でもその数が急増している「移動」する(国境を越えて育つ・複数の言語の中で育つ)子どもたち。現在各方面で活躍する「移動する子ども」だった大人達が、自身の心の軌跡を惜しみなく語る対談集。
推薦のことば:西原鈴子(日本語教育学会元会長)
10人の「移動する子ども」だった方々のお話は、複数の言語との接触が同時に複数の「生き方」との接触だと教えてくれます。これは移動というオプションで育まれた豊かなこころの軌跡の物語です。研究者にはわくわくするデータ、子育てをする人には得難い参考書、成長中の若者には力強い応援歌となることでしょう。
第一部 幼少の頃、日本国外で暮らし、日本に来た「移動する子どもたち」
1 セインカミュ(マルチ・タレント)
「外人」と呼ばれて、外人訛りのない日本語で返そうと思った
2 一青妙(女優・歯科医師)
台湾で中国語を話し、自分は台湾人と思っていた
3 華恵(作家)
ニューヨークで英語の本を読みふけっていた
4 白倉キッサダー(社会人野球選手)
長野に着いたとき、「タイ語、禁止」と言われた
5・6 響彬斗&響一真(大衆演芸一座)
ブラジルで日本舞踊、和太鼓、三味線、歌を習っていた
第二部 幼少の頃から日本で暮らし、複数の言語の中で成長した「移動する子どもたち」
7 コウケンテツ(料理研究家)
大阪で生まれ、大人が韓国語交じりの日本語を話すのを不思議に思った
8 フィフィ(タレント)
名古屋で育ち、アラビア語を話さなくなった
9 長谷川 アーリア ジャスール(プロサッカー選手)
埼玉で生まれ、イラン語を「使えないハーフ」と語った
10 NAM(音楽家・ラッパー)
神戸で生まれ、「ベトナム語は話さんといて」と親に言った
終章 川上郁雄
「移動する子ども」だった大人たちからのメッセージ
あとがき
【著者紹介】
川上郁雄(かわかみ・いくお)
早稲田大学大学院日本語教育研究科・教授
専門:日本語教育、文化人類学
1990年大阪大学大学院文学研究科博士課程単位取得。博士(文学)。オーストラリア・クイーンズランド州教育省日本語教育アドバイザー、宮城教育大学助教授・教授などを経て2003年より現職。国籍や言語や生活世界などにおいて、多様な背景をもつ子どもたちの「ことばの教育」(「移動する子ども」学)について研究を行っている。文部科学省「JSLカリキュラム」開発委員、同省「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会」委員。
編著書に『「移動する子どもたち」と日本語教育:日本語を母語としない子どもへのことばの教育を考える』『「移動する子どもたち」の考える力とリテラシー:主体性の年少者日本語教育学』『海の向こうの「移動する子どもたち」と日本語教育:動態性の年少者日本語教育学』(ともに明石書店)など。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぶんこ
しの
Nobu A
ロピケ
wannrenn