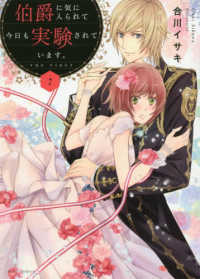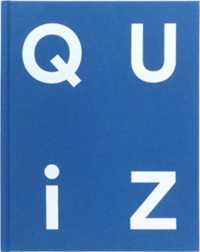内容説明
幕府のお墨付きを得て公然と行われた江戸の御免富に着目し、他の富突類似興行との相違や地方との比較、そしてさらに江戸の社会制度や文化史における位置付けを視野に入れつつ、「富くじ」を江戸趣味の範疇から、歴史学研究における近世都市江戸の解明の一つの切り口とする。体的には従来一面的だった江戸の御免富の形成・展開・衰退を系統立てて考察し、そのシステムを明らかにするとともに、御免富というシステムを幕府側・寺社側・庶民側という三者の角度からそれぞれ分析を加えて全体像を描き出すことで、請負構造や受容社会の問題、さらには江戸における御免富の存在意義を考察。そして江戸の御免富が行動文化の各要素に少なからず適合するとの想定のもと、行動文化を捉え直す上での作業とも位置付ける。
目次
第1部 御免富システムの成立と展開(御免富の誕生―由緒と享保の寺社助成策;御免富の規格化と請負システムの成立―明和~天明期江戸の富興行の構造;江戸における御免富の展開)
第2部 興行場所と請負構造(江戸の御免富興行における「場」;御免富における受入れ寺社の動向―新材木町椙森稲荷の事例から;富突にみる江戸の興行空間―浅草寺の富をめぐって;御免富の請負構造―文政~天保期の事例を中心に)
第3部 御免富の受容社会(庶民の富札購入と受容構造;富突の道具からみる受容社会―富札・富箱を中心に;おはなし四文と江戸社会―富突の光と影)
著者等紹介
滝口正哉[タキグチマサヤ]
1973年東京都生まれ。1996年早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。2005年立正大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。千代田区教育委員会文化財調査指導員。徳川林政史研究所非常勤研究生。立正大学非常勤講師。博士(文学・立正大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。