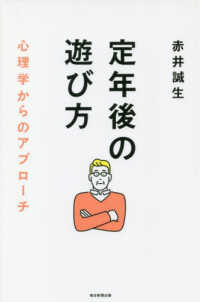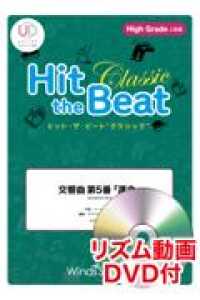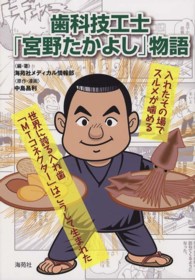内容説明
長野市ではじめられた研究仲間「古代中世史研究会」が、17年余にわたっておこなってきた地域での自主的研究活動の成果。地域の史料とフィールドにもとづきながら、信州や東国の視点から、アジアのなかにおける列島の歴史と文化を分析。歴史理論を探究しつつ、地域と民衆を主人公とした地域史・日本史学の構築をめざす。
目次
1 地域史と権力(科野(信濃)国造に関する考察
「麻續」の名称とその変遷について
十一世紀、東国における国衙支配と坂東諸国済例の形成―諸国未済物・債務処理システムの登場
一条高能とその周辺―姻戚関係と政治的役割)
2 前近代の技術と生業(古代遺跡出土の鉄鏃;武家の狩猟と矢開の変化;中世における大唐米の役割―農書の時代への序章)
3 寺社と信仰(平安時代初期の天台教団について―恵亮を中心に;善光寺信仰と女人救済―主として中世における;信濃国太田荘における熊野社勧請の意義について;小笠原貞宗開善寺開基説成立の背景;地方曹洞宗寺院の文書目録作成の歴史的意義―如仲天〓(ぎん)との関わりから)
著者等紹介
井原今朝男[イハラケサオ]
1949年生。国立歴史民俗博物館歴史研究系教授、総合研究大学院大学教授
牛山佳幸[ウシヤマヨシユキ]
1952年生。信州大学教育学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 基礎からの英語