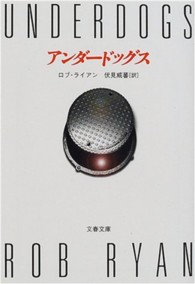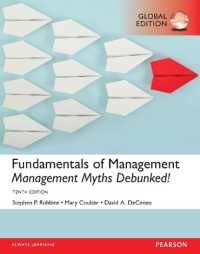内容説明
本書の構成は、第一章「鬼子」の民俗、第二章「鬼子」の文化史、第三章初誕生儀礼における「鬼子」、となっている。第一章の「鬼子」の民俗では、「鬼子」の今を問い、伝承の中で「鬼子」がどのように語られて来たか、人々の記憶の中にある「鬼子」の姿を浮き彫りにする事に努めた。第二章の「鬼子」の文化史では、明治以前から古代に至るまで、文献史料の中に見える「鬼子」像を一つ一つ吟味し、歴史的に変遷して来た部分と、時の経過にも関わらず古代以来殆ど変わらなかった部分がある点を明らかにした。第三章の初誕生儀礼における「鬼子」では、一歳未満で歩いた子供に限定して転倒目的で餅を背負わせ、それでも倒れずに歩く子供を「鬼子」と称し、これを強制的に後ろから突き倒す習俗に注目した。
目次
第1章 「鬼子」の民俗(辞書類にみえる「鬼子」;民俗語彙としての「鬼子」;大正から昭和にかけての「鬼子」の報告事例 ほか)
第2章 「鬼子」の文化史(明治期から近世初期にかけての「鬼子」;中世の「鬼子」;古代以前の「鬼子」 ほか)
第3章 初誕生儀礼における「鬼子」(一歳未満で歩く子供を「鬼子」と呼ぶ類例;「王子」から「鬼子」へ)
著者等紹介
近藤直也[コンドウナオヤ]
1954年生まれ。1976年、関西大学文学部史学科卒業。関西大学大学院博士課程後期修了。文学博士。長崎県立大学教授を経て、現在、九州工業大学情報工学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
eirianda
0
出る杭は打たれる。高貴な出自の鬼子の伝説が日本では普通の家庭の異形の子どもとなったあたりが、なんとも日本らしく、世間の秩序を重んじるがゆえに子を遺棄するとは……なんとまあ、日本の民族の小市民っぷりが、いまもなお受け継いでいるように感じるのは私だけだろうか? 出た杭はいろいろ使い道がある、って諺も変えたほうがいい。あとがきの人がホラーを好きなわけ、は納得。生きてるわ! 私!2012/11/01
和沙
0
一部、明らかな間違いあり。「宋居士」の宋は、六朝の劉宋のことです。2010/06/02