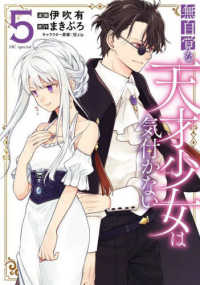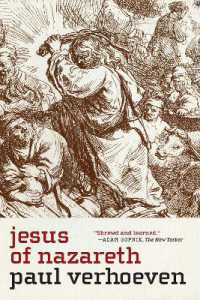内容説明
中華帝国、モンゴル帝国、イギリス帝国、「覇権国家」…「関係」と「比較」をもとに世界の歴史をとらえ、いま、歴史学界で注目を浴びるグローバルヒストリー。
目次
序章 グローバルヒストリーと帝国
1章 モンゴル帝国と中国―コミュニケーションと地域概念
2章 モンゴル・シーパワーの構造と変遷―前線組織からみた元朝期の対外関係
3章 中世大越(ベトナム)の農村社会に関する比較史的検討
4章 一八世紀のイギリス帝国と「旧き腐敗」―植民地利害の再検討
5章 近代帝国の統治とイスラームの相互連関―ロシア帝国の場合
6章 一八~一九世紀の北太平洋と日本の開国
7章 日清戦争論の現在―帝国化の起点をめぐって
8章 綿業が紡ぐ世界史―日本郵船のボンベイ航路
9章 チャールズ・A.ビアードの反「帝国」論再考―東アジア体験との関連を中心に
著者等紹介
秋田茂[アキタシゲル]
1958年生まれ。大阪大学大学院文学研究科・世界史講座・教授
桃木至朗[モモキシロウ]
1955年生まれ。大阪大学大学院文学研究科・世界史講座・教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
読書実践家
3
従来の西洋中心から脱却した歴史の見方が響いてくる一冊。2021/07/06
湯豆腐
1
M木氏が事あるごとに「阪大歴史学の挑戦」を礼賛するのでなんぼのもんじゃいということで読んでみた。結果、なかなかに面白い。特にインド・日本・中国の綿工業を主体とした貿易がイギリス帝国を中心とした国際体制の中でアジアの相対的自立性を高めたという論は興味深かった。ただ、「グローバルヒストリーと帝国」をテーマにした本でわざわざ出さなくてもいいのでは、という論文も見受けられる。2015/05/11
某准将(珈琲好き)
0
確かにお手頃かつ多種多様な論集でした。どれもなかなか面白かった……とくにモンゴル・シーパワー。2013/05/16
-

- 洋書電子書籍
- Using Your Voice Ef…