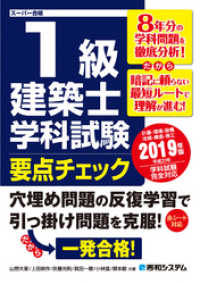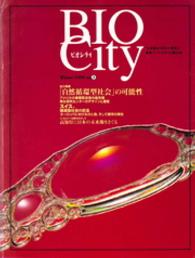内容説明
日本史・アジア史・西洋史の全体をとらえ、歴史の魅力を探る。歴史によせる高校・大学・市民の期待に向き合う阪大歴史学の成果。
目次
第1部 歴史学の危機と挑戦(現代社会の歴史離れと歴史教育の混乱;歴史学の限界と動脈硬化;そもそも歴史学とはどんな学問か;歴史学の論理展開;新しい歴史学の躍動;阪大史学の挑戦)
第2部 東南アジア史の可能性(東南アジア史とその研究視角;役に立つ東南アジア史;面白い東南アジア史;わかる東南アジア史)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tetuneco
6
歴史って事実をどう綴るかが大切。どう見せるかが大切。なんだと思う。。2011/12/30
さとうしん
2
歴史教育に特化した史学概論本。前半が日本の歴史教育と歴史学研究の問題点について、後半が著者の専門とする東南アジア史の教育について。歴史用語の暗記にこだわる日本の歴史教育は、長文の暗記(論理の暗記もその中に含まれる)を求める中国・韓国の教育にかなわない、日本の文化は中世までは東南アジアの文化と類似していたが、江戸時代の「鎖国」によって東南アジア的な文化が失われたなど、本筋とは関わらない小ネタもなかなか読ませる。2016/04/15
bassai718
1
まえがきで注を読んでほしいとある通り、注の充実と熱量がすさまじい(むしろこちらで本音をぶっちゃけているとも)歴史教育についての批判的な論考だが読み物としてもおもしろい。2025/10/09
葛城
1
主張はよく分かる。現場に気を遣っているのも分かる。だが、実際限られた授業数で教えるにはキツイ。生徒の理解を斟酌しないでジェットコースター的に教えるのがいいのか、中途半端な範囲でもじっくり教えていくのがいいのか。2010/09/21
Humbaba
1
一言に歴史と言っても,その中には日本史やアジア史,西洋史といった横の分類から,古代史や近代史,現代史までの縦の分類など様々なものがある.それらの全体を捉えることで,今までとは違った歴史観を持つことができるようになる.2010/08/10