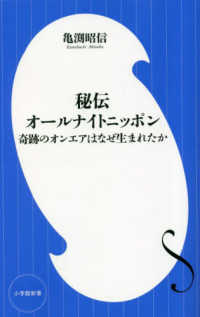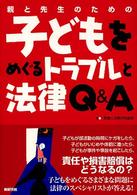内容説明
中欧世界に浮かびあがる芸術文化の立体像。中欧を舞台にくりひろげられてきた、近代ドイツの芸術と社会のせめぎあい。その歴史を、表現活動と日常生活との密接なつながり、ドイツとユダヤの共存の夢、現代社会と斬りむすぶモダニズム芸術の挑戦という3つの位相から追っていく。芸術文化の奥行きにふれる、読みごたえあるガイドブック。
目次
1 表現のかたち―個人と社会をつなぐもの(近代への飛翔―博物学に魅せられた画家メーリアン;啓蒙のメディア―読書と市民社会;声の始源―口承文化を発見した人びと;ピアノのある部屋―市民的教養としての音楽;祝祭の共同体―ワーグナーの綜合芸術プロジェクト)
2 共生の夢―ユダヤとドイツ(聖書の民―中東欧ユダヤ人の源流;対話から同化へ―メンデルスゾーン家の人びと;境界の文学―ハイネとドイツ;存在と帰属―カフカ家三代の歴史から)
3 モダニズムのゆくえ(カウンターカルチャーの輝き―世紀転換期の青年たち;挑発するメディアアート―ハンナ・ヘーヒ、「騒然たる時代」を調理する;越境する批判精神―フランクフルト社会研究所と亡命知識人;オスタルジーの彼方へ―ドイツ統一と東ドイツの現実)
著者等紹介
三谷研爾[ミタニケンジ]
1961年生まれ。大阪大学文学研究科博士後期課程中途退学。大阪府立大学総合科学部をへて現在、大阪大学文学研究科准教授。専門分野はドイツ・オーストリア文学、中欧文化論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ばん
3
ドイツ文化史だが、昔のことについては美術史か、民俗歴史学になるだろう。この本は近代の夜明けくらいからの文化について書かれている。(まあ文化っていう考え方とか、文化史的に捉えるとか、そう言う方法が通用するのが近代くらいからなんだろう。啓蒙の中で生まれて来る考えだろうし、少なくとも教養市民層が形成されて、浸透していかない限りは、文化、なんて考え方は難しい。当然ナショナルリベラリズムとか、19世紀に極まるドイツナショナリズムとか家父長制を考えた方がいい。)特にピアノとかワーグナーとか、昆虫についてが面白かった。2012/09/30
Meroe
1
啓蒙と出版文化、口承文化の発見、ユダヤ人、ダダにフランクフルト学派にオスタルジーなどなど、導入になってここから広げていける感じ。ドイツ文化、に関する本につきまとう岩波文庫臭がなく読みやすい。阪大リーブルはこういう本が多いのかな?いろいろ読んでみたい。2011/08/01
浜町
0
久々にドイツに関する本を読んだ。一番興味深かった項目は、ハンナ・ヘーヒとダダイズム。彼女が発表したキッチンナイフを改めて見ると色々と考える。2016/11/12
にたす
0
大学入学直後に登録し、初回だけ出て登録を抹消した教養科目で教科書に指定されていたもの。そこそこおもしろかったが、そもそもドイツの歴史・地理をほとんど知らないので各章の内容が頭の中でまとまらない感じ。2011/05/28
nob_de
0
論文集なので一概にコメントは付けられない。オスタルギー(オスタルジーと記述)の章で、ヒルビヒ著『私』の引用部分「ウーンーコー、ウーンーコー、ウーンーコー」が熱い。2009/12/21