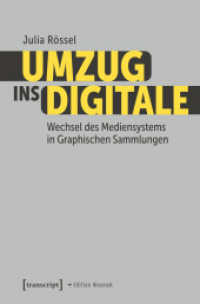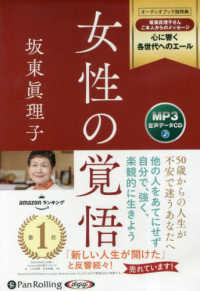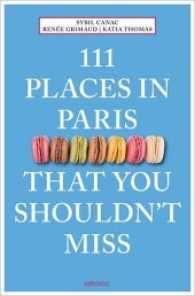目次
第1章 バウハウスの一般的理解(モダン・デザインの到達点;機能主義の象徴;近代合理主義、モダニズムの代表)
第2章 バウハウスの歴史的背景(近代合理主義について;ペヴスナーの歴史観と技術史の展開;ワイマール共和国および政治とのかかわり)
第3章 バウハウスの成立から閉鎖まで(ヴァルター・グロピウス;バウハウスの確立―グロピウス構想の体現;グロピウス後のバウハウス)
第4章 バウハウスの本質的理解(バウハウスの技術観;バウハウスの芸術観;バウハウスの建築観;バウハウスの人間観;バウハウスの世界観)
第5章 バウハウスの今日性(バウハウスを受け継ぐ教育機関;芸術におけるバウハウスの今日性;政治と芸術の関係性―バウハウスの教訓;バウハウスの寛容性、無限性、倫理性)
著者等紹介
阿部祐太[アベユウタ]
1982年東京生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻修士課程修了。文化と政治の関連性をテーマにした社会学的研究に取り組むとともに、文化総合の観点から歴史や倫理、現代政治の研究も行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
aof
4
バウハウスの組織のあり方に現代社会が求めるものが重なると思って、その閉鎖までのプロセスを興味深く読んでいたけど、最後のバウハウスに足りなかったものとしての作者の考察がすごく良かった。自分に刺さるというか。 社会活動は社会の中で起こっている以上、政治的であり中立にはなり得ない。だからこそ、政治や権力を絶対悪とするのではなく、その思想を知り、政治的な視点を持ったうえで社会実践をすべき、という。 わたしも政治は大嫌いだけど、ちゃんと知らないといけないなーと思わされた。 【図書館本】2020/03/10
林克也
1
この本、“バウハウス=バァルター・グロピウス”を看板にしてはいるが(それはそれでとても参考にはなったが)、本質は、現在のニッポンの閉塞感をブチ破るために阿部祐太が政治論を表明した本だった。教養としてこういう知的な本を読む人は限られた層であろうし、自分も含めて、行動に移すことのできる人ははるかに少数だろう。特に、今のニッポンでは、表向き3割、実質1割以下の無教養層を利用して世界一バカで恥知らずな政治屋を操る輩が支配している状況を打破できずにいる知識層は座して死を待つのみ。あー、悔しい。悔しい。悔しい。2018/05/12
すすむすすみ
0
バウハウスの精神性や社会面にフォーカスして書かれた本。 前半のバウハウスの成り立ちやそもそもどんな機関だったのかの記述が面白い。 職人と親方的な師弟関係のある教育施設のイメージあんまりなかった。2025/04/20
noppo
0
で結局バウハウスって何なの? という問いに対して、当時の状況から取り巻く環境などをちゃんと順序だてて説明してくれる。それが4章まで、最後の章だけ著者の考えが多いのでそこだけ割り切って読めば入門としてとってもいいと思う。 2019/02/03