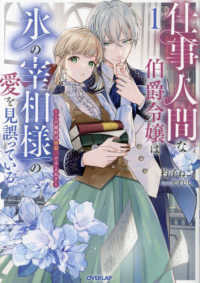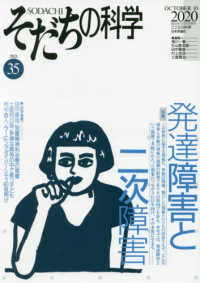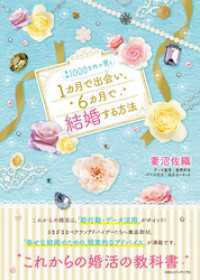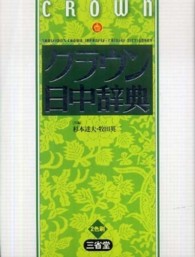内容説明
5日間のワークショップで実証される驚異の右脳パワーの謎。“描く”とはいかなる行為かを徹底的に解明。ユニークな美術教育と、最新の脳研究から生まれたメソッドの決定版。
目次
画を描くことと自転車に乗ること
画の実習、一歩ずつ
あなたの脳の右と左
クロスオーバー、左から右への転換を体験する
記憶を引き出す、画家としてのあなたの経歴
シンボルを回避する、端部と輪郭との出会い
スペースの外形の知覚、ネガのスペースの肯定的側面
新たなモードによる相互関係、目測による遠近法
前向きに、やさしい肖像画
論理的な明部と暗部の価値
色彩の美しさを引き出す
描くことの禅、内なる画家を引き出す
著者等紹介
エドワーズ,ベティ[エドワーズ,ベティ][Edwards,Betty]
カリフォルニア州立大学教授。美術教育の体験を生かし、ロジャー・W・スペリーらの脳研究にヒントを得て、短期間に写実的な画が描ける独自の指導法を開発し、高く評価される。近年は、美術教育にとどまらず、創造性全般を探求し、ワークショップやセミナーを主宰している
北村孝一[キタムラコウイチ]
1946年生まれ。早稲田大学文学部露文科中退
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
booklight
27
錯視ってありますよね。同じ長さの線が違って見えるやつとか <ー> >ー< 。つまり脳は事実を曲げる。曲げた状態、脳の感じたままを絵で再現しようとすると、事実と違うわけだから、当然うまく再現できない。だから事実を曲げないように見て、見たままを描く。ここがコツ。感じたものと事実は違う、というのは色々な示唆に富んでいる。理解したうえでの実技で、頭ではなく体感重視が新鮮。ちょっと禅とかにも似ている。文章はもう少しまとめてもらえるとありがたい。2018/09/02
booklight
26
【再読】今度は実際に描いてみる。なるほど、右脳的な要素と左脳的な要素を実際に感じる。透明な下敷き越しに自分の手を描いてみると、驚くほどうまくかける。どれだけ見たままに描いていなかったか、どれだけ左脳的・意味の方によっていたかが分かる。見たままに描くということは、見た比率通りに描くということで、理解や感性によらないのが面白い。立体を描く時、線を描く時は2次元、見る時は3次元になるのが変に気持ちいい。描くことに集中して意味を忘れている状態が、禅・マインドフルネスに似ている。大脳新皮質によっている自分を実感。2020/07/04
浮かれ帽子屋
19
絵を描くため、そして対象を捉えるための手法を学ぶ一冊。そしてそのための右脳の使い方を段階的なワークショップとともに教えてくれる。左脳に対して、右脳は非言語的/総合的/具体的/類推的/非時間的/非理性的/空間的/直感的/全体論的な思考に優れ、それは普段文章を読んだり情報を扱う左脳とはまったく異なる思考方法だ。それを、端部の知覚/スペースの知覚/相互関係の知覚/明部と暗部の知覚/全体の知覚(ゲシュタルト)という構造とともに教えてくれる。単に美術にとどまらない、脳の働きと使い方が分かる良本。読むだけでも面白い。2011/11/27
piro5
5
自分でも絵を描ける気がしてきた。この本には大切な事が書いてある。1つは、モノの見方が知覚を切り開くということ、1つは、それが世界の見方を変えてしまうということ。2011/04/17
pianomans
4
課題として本に載ってる人物の逆さ絵を描いてみたら、「足」のところで混乱。そしてこの混乱こそがRモードだったんだと実感。逆さで描いてる時はただの線だったのに、描き上げた絵を元に戻すとちゃんと「足」だった2012/06/17