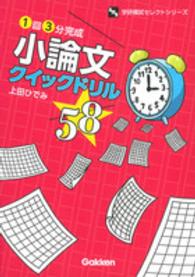内容説明
“今”必要なことは、「二段階人格形成論」の7つの発達課題に関心を持って「育て直し」に取り組むことです。自分の発達段階までは相手を「育て直す」ことができます。「育て直す」ことで自分の発達段階が確かなものと確認できます。親をはじめ大人にしてもらった乳幼児体験を、それを必要としているあなたの周りの人にすることです。正の連鎖、正の繰り返しをすることです。自分に不足している、あるいは未だ体験不足の発達課題は、それを認める努力をして、子どもでも大人でも仲間でも、確かな乳幼児体験をさせてもらうことで「育ち直る」ことができます。1人では乳幼児体験はできませんので、気持ちよく乳幼児体験できる人を大切にし、そこで気持ちよく乳幼児体験をすることです。今こそ、外見的な「自立」ではなく、子育てや保育、心の教育を通して、内面的な「自立」に取り組むことです。それは、生き甲斐を感じることになり、自己実現がはかれることだと思います。そして、学校教育を受ける前提としての乳幼児体験は、微笑むことで感情の表出ができていること、安全感覚で身を守る基礎ができていること、人への基本的信頼感(見捨てない人との出会い)を持っていること、言葉で表現し、言葉を理解する基礎ができていること、意志を持ったら、譲ったり譲ってもらったりする基礎体験ができていること、です。
目次
第1章 なぜ今、子どもも大人も「育て直し」「育ち直り」が必要か
第2章 保育における事例検討の必要性とその方法
第3章 思春期の子どもから大人までの「育て直し」「育ち直り」
第4章 保育者と保護者へのメッセージ
第5章 事例検討(1)「気になる子と親」に取り組む保育者への援助
第6章 事例検討(2)「虐待」にどのように取り組むか
著者等紹介
角田春高[カクタハルタカ]
昭和46年3月、愛知県立大学文学部社会福祉学科卒業と同時に、愛知県職員となる。愛知県心身障害者コロニー短期母子療育施設「緑の家」でケースワーカーを皮切りに、児童相談所、保健所、福祉事務所、保育大学校に勤務。乳幼児から老人世代までの相談活動から一生の中での「今」に相談に乗ることを学んだ。昭和58年頃、精神障害者とのデイケア活動や相談活動を通して「育て直し」を着想。さらに、子どもは7つの発達課題を繰り返して大人になると「二段階人格形成」を構築し、その後の相談活動で検証を重ねてきた。また、昭和61年から保育者との事例研究会でスーパービジョンに取り組む。平成5年4月から保育大学校で教鞭を執るとともに、気になる子に対する「育て直し」保育の検証と普及に努める。平成11年4月、愛知学泉短期大学幼児教育科教授となり、保育者養成と現職教育で「二段階人格形成」による「育て直し」を提唱、普及に努める。臨床心理士。あいち子どもケア研究会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- しゃれた言葉 講談社文庫