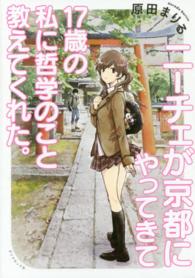出版社内容情報
助動詞が動詞の複語尾とも言うべき「意味」と「機能」を有するものである事を、主として中古助動詞によって論証。時枝詞辞論批判が一つの大きな眼目で、特に「意味」の面から時枝詞辞論を体系的に批判した書である。
内容説明
本書は、先著『助詞の構文機能研究』に対となるべき、これまでの助動詞に関する諸論をまとめたものである。論の中心的対象は中古語であるが、その基本的成果は現代語にも通ずるものと考える。本書の結論は、端的に言えば、助動詞は動詞の複語尾(乃至それに準ずるもの)であり、動詞の一部(乃至それに準ずるもの)として種々の構文機能を担う。という事である。
目次
第1章 「連体なり」の構文的意義(「連体なり」構文の基本構造;主述句「連体なり」構文の構造 ほか)
第2章 助動詞の構文的機能(「らむ」構文の構造;「なるらむ」構文の構造 ほか)
第3章 助動詞の「意味」的機能(「む」の「意味」;時枝詞辞論解釈 ほか)
第4章 助動詞と周辺の応用的考察(「む」におけるテンス機能;命令表現の詞辞性 ほか)