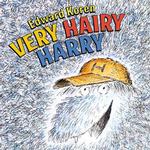出版社内容情報
第1章 “子どものリアル”が見えますか?
小学校校長も望む“児童への深い理解”・・・・・・・・●
1 子どもの心の奥の声に耳を傾けて―“熱い胸と冷たい頭”
(1) 「荒れ」と呼ばないで!―2年生・隆君?喧嘩と悲鳴の始業式″・・・・●
気になる言動が増えた背景 ●/トイレに行く暇もない疲労困憊のクラスで ●/
国語―詩「ねこ殿へ」が心を動かす ●/床に投げ捨てたプリント―隆君の胸の内 ●/
算数―「ウサギ+ニンジン」で本質を突いた隆君 ●/トラブルを起こす背景
(2)“わからない辛(つら)さ”が、わかりますか?―5年生・英雄君の涙
「お前はいいよな。宿題をしなくても怒られないんだから」 ●/
たいへんだけど、がんばってべんきょうしています ●/わが子の願いを受け止める ●
(3)“良い子の辛(つら)さ”が、わかりますか?
「良い子」の異変 ●/1年生の1学期に通知表を改ざんした「良い子」 ●/
1年生・ひかりさんの?プリントすり替え事件″―その心は・・・ ●/
世代を越えた“競争の価値観”の問題 ●
(4) 子どもの見方、“子ども観”を育てる
教育実習生の“子ども理解”と“子ども観”の変化 ●/“子ども理解”?新米先生の成長 ●/
子どもの“キラリ変化”を見つける目を養う ●/「見えないものを見ようと努力する」教師に ●
2 大人の「価値観」こそ問われている
(1)子どもへの眼差し・価値観は・・・・・・・●
ごみ箱に捨てられたテスト・・・3年生・良美さん ●/世界から日本の子どもを見ると・・・ ●
(2)?失敗・間違いは宝“
自己肯定感の低い子を育ててしまう算数授業 ●/自分の考え方に×をつける子ども―4年生研究授業● 失敗や「間違い」から「腑(ふ)に落ちる」納得を作る ●/
「3にん」と「3にんめ」の違い―「討論」で納得! ●/競争から共生への転換を ●
第2章 自分が好きになる“学び”を作ろう―具体例で見る“子ども理解”と“学び”―
1 「できるようになりたい!」子どもの願いに応える学びを、どう作るか
「学校は好きですか?」「授業時間は好きですか?」・・・・●
(1)教師が変われば子どもも変わる!―破壊と授業不成立の学校で・・・・●
“学ぶ子どもが主人公”の確認で再出発 ●/“子ども発見”をした「比例」の学び ●
(2)1年生の育ち合い―友だちと関われず、学習に興味ない子の成長・・・・●
「ありがとう」が言えた明君 ●/子どものありのままの表現を書き直す指導?―私の苦い経験 ●/
明君が一緒に遊べる方法を考えようよ!?1年生の提案 ●
(3)1年生、初めての授業参観―親も子も緊張と不安でいっぱい・・・・●
1年生の親の不安 ●/初めての授業参観―国語「そ」の学習 ●
(4)“待つ”ことの大切さと難しさ―初めて長文を書いた!(3年生)・・・・●
「どうしても書きたい!」 ●/“待つ”ことは難しい ●/
2学期「国語」「すがたをかえる大豆」が転機に ●
2 小さな「問い」を大きな「学び」に育てよう
(1)一人の興味がクラス全体の学びにつながる時・・・・●
怒られた失敗談から、草木染学習への発展―2年生 ●/子どもが子どもに教える≪漢字先生≫ ●
(2)ミミズからブドウ、そしてパンへ―総合学習に発展・・・・●
始まりは≪朝の発表≫ミミズの報告―3年生 ●/
ブドウ?酵(こう)母(ぼ)?パン作りへ―地域の素敵な大人との出会い ●/
落ち葉の発酵を五感で知る ●/子ども自身が学びの主体となる学習観を ●
(3)雑木林を切らないで!―行政を動かした子どもたち・・・・●
雑木林を切らないで! ●/「ブナの森は緑のダム」を学ぶ―6年・国語 ●
(4)教室を飛び出す算数が楽しい!―生活と仲間を結ぶ算数・・・・●
『オムツの取り換え問題』から広まった問題作り―3年生 ●/
1000?ないよ!牛乳パックの不思議発見!―5年生 ●/液量の学びも体験で ●/
セシウム137と134?―そのヘーゼルナッツ、待った! ●/「観」を育てる ●
第3章 “安心の居場所”をどう作るか
1 安心の居場所としての教室をつくる工夫
(1)大切な朝の「ひと時」の工夫・・・・●
大切な初めての出会い・・・握手・プレゼント・遊び ●/呼名“ひと言”プラス ●/
≪朝の発表≫で、子どもの生活や興味を交流 ●
(2)生活や興味の交流の場≪朝の発表≫・・・・●
≪朝の発表≫のテーマ・発表形式は、自由 ●/
一人の興味・遊びが、仲間につながっていく≪朝の発表≫ ●/
クッキーを焼いて≪朝の発表≫?みんなの分も作ってきたよ ●/
母の日にお父さんにあげたカーネーション―胸の内を語り合う≪朝の発表≫ ●/
体重測定で嫌なことを言われた―不満も伝える≪朝の発表≫ ●
(3)「ヒト・モノ・コト」と出会う≪探検活動≫・・・・●
≪探検活動≫で教室を飛び出そう! ●/≪探検活動≫の準備 ●/
5年生・算数で、教科書に≪探検活動≫! ●/5年生・社会科「米作り農家」で≪探検活動≫ ●
(4)“綴(つづ)り”“自分を語り”“交流する”・・・・●
授業を綴(つづ)ると見える“新しい世界と自分発見・友だち発見” ●/
≪授業日記≫―“学びを書き綴(つづ)る”意味 ●/
「2枚のパンを3人で分けると、1人分はいくつ?」の≪授業日記≫ ●/
綴(つづ)ることで学びの主体が育つ ●
2 “遊び”“文化活動”で仲間づくり
(1)“遊び”は体を心を解放し、子ども同士をつなぐ・・・・●
(2)≪民舞≫「荒馬」のリズムが子どもの飛躍をつくる・・・・●
「荒馬」が薫さんを変えた ●
(3)≪詩の発表会≫―生き生きとパフォーマンス・・・・●
2年生・萌子さんたちの『のはらうた』パフォーマンス ●/≪詩の発表会≫の魅力 ●/
もめ事も大事 ●
(4)多様な表現の場、≪劇遊び≫は学級のまとめの会で・・・・●
2年生、『どろぼうがっこう』で≪劇遊び≫ ●
(5)≪学級文化活動≫と自治活動・・・・●
≪誕生会≫で、一人ひとりが主人公 ●/≪学級クラブ≫は、楽しい活動 ●
(6)教室空間を変える!―机の配置・・・・●
≪提案ボード≫ ●
「体育着を変えて欲しい!」―要求を実現した子どもたち・・・・●
社会の大切な担い手の一人として育つ ●
第4章 教師って本当にステキな仕事?!―疲れ・悩む教師のQ&A
1 愚痴をこぼそう・相談しよう・みんなで考え合おう
*新任教師です。疲れています! ・・・・●
*ベテランも語る!・・・この仕事、希望はどこに?・・・・●
2 「子どもの見方」を育てよう! 実践を綴って、学び合い
*どうしたらいい?騒ぐ子どもたち―子どもの現実中に解決の道はある・・・・●
*活発に意見が言えるクラスにしたいけど・・・・・・・●
*「甘い顔をしないで、厳しく指導するべき」と言われるけれど・・・・・・・●
*子どもたち同士のトラブルや「問題行動」をどうする?・・・・●
3 子どもを真ん中に考えよう!―子どもを語り、明日の授業をつくる
*「学力テスト」の成績に追われてばかり。「こなす授業」から抜け出したい!・・・・●
4 子どもを真ん中につながろう!
*クームをどう受け止めるの?・・・・●
*虐待・困難を抱えた子どもたちを、どう把握するの?・・・・●
コラム? ワクワク「円」の学習は、玉入れから ●
コラム? ≪えつこの部屋≫とご褒(ほう)美(び)のおんぶ ●
コラム? 九九はできないけど、42÷9がわかった! ●
渡辺 恵津子[ワタナベ エツコ]
大東文化大学准教授。日本生活教育連盟副委員長。埼玉大学教育学部卒。2011年3月まで、38年間小学校教諭として勤務。
著書=『こどもといっしょにたのしくさんすう 小学1?3年編・小学4?6年編』
目次
第1章 “子どものリアル”が見えますか?(子どもの心の奥の声に耳を傾けて―“熱い胸と冷たい頭”;大人の「価値観」こそ問われている)
第2章 自分が好きになる“学び”を作ろう―具体例で見る“子ども理解”と“学び”(「できるようになりたい!」子どもの願いに応える学びを、どう作るか;小さな「問い」を大きな「学び」に育てよう)
第3章 “安心の居場所”をどう作るか(安心の居場所としての教室をつくる工夫;“遊び”“文化活動”で仲間づくり)
第4章 疲れ・悩む教師のQ&A―教師って本当にステキな仕事?!(愚痴をこぼそう・相談しよう・みんなで考え合おう;次々に起こるトラブル―実践を綴って、「子どもの見方」を育てよう! ほか)
教師として育つとは?―“子どもと共に育つ伴走者”―終わりにあたって(求められる2つの“そうぞう力”;“共生”の価値観を育む4つのポイント ほか)
著者等紹介
渡辺恵津子[ワタナベエツコ]
大東文化大学特任准教授。日本生活教育連盟副委員長。埼玉大学教育学部卒。2011年3月まで38年間小学校教諭として勤務(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。