内容説明
ジャパニーズ・ホラー作品を通して研究する、現代日本の幽霊文化。
目次
第1章 Jホラーと幽霊研究
第2章 『邪願霊』と心霊写真
第3章 『リング』と超心理学と伝染る怪談
第4章 ビデオ版『呪怨』と“場”に固定化した幽霊
第5章 『回路』と幽霊の氾濫
補章 幻影の車
著者等紹介
大島清昭[オオシマキヨアキ]
1982年(昭和57年)生。2007年筑波大学大学院修士課程地域研究研究科修了。占術家、妖怪研究家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mittsko
7
表題の「Jホラー」とは当然、映画作品のこと。『リング』『呪怨』を『邪願霊』と『回路』ではさむ構成。一見妥当な並びに見えようが、映画史としては実は腰が大いに弱い。映画論としても、いかにも素人くさい(実作者は逆に喜ぶかもしれない)。ただし、映画作品は素材にすぎず、本書は幽霊研究なのだと著者本人は言う。よって、評価はそちらでするのがフェアなのだが、こちらはこちらで問題設定、立論、結論がすべてグズグズになっちゃっており、研究の名に値しない。長大な読書メモを読まされている感覚になりました。これじゃダメ、残念!2023/08/21
crpsclr
5
2010年6月20日第1刷。『邪願霊』、『リング』、ビデオ版『呪怨』、『回路』を中心に、Jホラーにおける幽霊を論ずる。Jホラーにおける表象様式の分析ではなく、幽霊そのものが近現代においてどのように人間の前に現れてきたのかに主眼を置く。「生者」、「死者」、「可視」、「不可視」を基準とした独自の「霊魂チャート」(18)を作成し、それをもとに論を進める。著者は「感染」の観点から幽霊を捉え、論全体に敷衍している。「近代スピリチュアリズムと心霊研究」(19-30)、「心霊写真の歴史」(44-56)が勉強になった。2022/02/20
ekura
3
どうも著者の論考はまとまりがないと思っていたが、理由がわかった気がする。著者が論考を制御できていないのだ。目の前の論の展開に著者自身が引きずられ、結論がどこかへ行ってしまう。 たとえば第4章は『呪怨』は新しい幽霊表象であるが、その性質は地縛霊=場に固定化された霊であり、民俗文化にも根付いた存在であるとする。ここまでは文句ない。賛同する。そして「その呪怨の霊は犠牲者に憑いて移動すること」に注目し、その性質を整理しようとする。ここも問題ない。賛成するし論旨も整理もわかる。(つづく)2021/07/06
akee
3
もうひと押し欲しかったけど面白かった。 めっちゃリングみたい。2019/11/03
HANA
2
現代の幽霊観を論じた一冊。Jホラーを論じたものかと思っていたため、少し肩すかしを食らわされる。リングと感染、呪怨と地縛霊と連想はありきたりであるが、手際よくまとめているため読んでいて面白い。ただ、先行する研究をまとめた物で目新しさを感じられないのが難点かも。2010/07/11
-
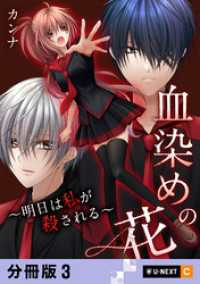
- 電子書籍
- 血染めの花~明日は私が殺される~ 【分…








