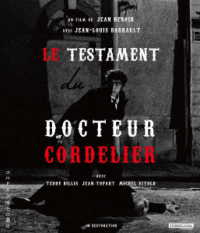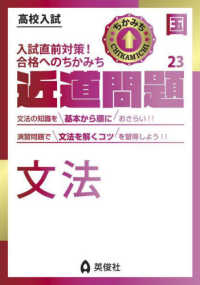内容説明
高齢者として知るべき、学ぶべき、考えるべき3つのこと。1.高齢者をめぐる社会的な状況、特に日本で広がる「老いを嫌い・憎悪する」=「嫌老」という社会的風潮とその背景を知る。2.「嫌老」に立ち向かう理論を、国際的な最新の「老年学(高齢者研究):ジェロントロジー」から学ぶ。3.「社会参加」「老いの進行」「死の接近」という課題への対応を通して、老いと死を見据えながら、社会とかかわる「高齢期の生き方」を考える。
目次
1 「嫌老」と「高齢者学習」(「敬老」から「嫌老」へ「高齢者受難の時代」の到来;「高齢者教育」の否定から「高齢者学習」の提起へ ほか)
2 人間の「進化」と「高齢者」の役割(人間の一生の「区分」と「高齢者」の役割「おばあさん仮説」から学ぶこと;人間の「進化」と「助け合い・支え合い」 ほか)
3 「現役引退(隠居)」と「生活」への回帰(「現役引退」としての「隠居」のすすめ;現代の三つの社会システムと「生活」の位置付け ほか)
4 「社会参加」と「健康維持」「終活」(「高齢期」の3段階の特徴と「生活課題」;「高齢者」の「社会参加」とその類型 ほか)
著者等紹介
小櫻義明[コザクラヨシアキ]
1945年、広島県生まれ。1974年、京都大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。大学での研究分野は「経済学地域政策論」。同年、静岡大学人文学部経済学科へ赴任し、「静岡地域学」を生涯のテーマとする。以来、専門分野にこだわることなく、アカデミズムに背を向け、自治体の政策・施策・事業の研究調査を行い、静岡県や静岡市などの自治体の各種の委員も数多く歴任。地域住民による「地域づくり(まちづくり・むらおこし)」にも強い関心を持ち、静岡県内の地域づくり団体の交流や、先進事例の視察・調査を行い、助言者・講師としても活動。妻の死後、2年間は引きこもり状態だったが、現在は回復し、自身の研究の取りまとめを行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。