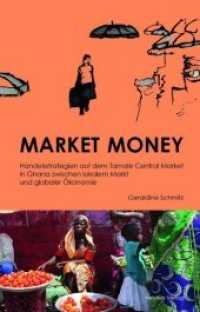出版社内容情報
今もサハリンに生きる何人もの日本人・日系人のもとに通い、話を丹念に聞きカメラに収めた渾身のドキュメント。戦後70年あまり、ロシア・サハリン(樺太)では、多くの日本人が現在も暮らし続けている。
過酷な境遇を生き抜きいた彼らの顔、表情、そして、日々の営み──
ひとりの若手写真家が、現地で10年以上取材を続けて撮影し書き上げた、渾身のドキュメント。
なぜ多くの日本人が、戦後も祖国に帰れなかったのか?
今もサハリンに生きる何人もの日本人・日系人のもとに著者が何度も足しげく通い、
家族のように一緒に泣いたり笑ったり、実の孫のようにかわいがられながら関係を深め、
話を丹念に聞きカメラに収めた、彼女たちの波乱に満ちた苦しい過去、そして穏やかで平和な今の暮らし。
「もうあと10年もすれば、私たちはまたひとつの世代を見送ることになるだろう。
その時にはこの写真の持つ意味もはっきりと理解できるのかもしれない」
──著者あとがきより
解説: 玄 武岩(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 准教授)
ロシア語版解説 パイチャゼ スヴェトラナ(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 助教)
後藤悠樹[ゴトウハルキ]
著・文・その他
内容説明
戦後70年、ロシア・サハリン(樺太)では、多くの日本人が現在も暮らし続けている。過酷な境遇を生き抜いた彼らの顔、表情、そして、日々の営み。現地で10年以上取材を続けた若手写真家、渾身のドキュメント。
目次
木村さん―2014年
松崎さん―2014年、2015年
ハツエさん―2009年、2013年、2014年、2015年
白畑さん―2014年
グリーシャさん―2015年
ユリ子さん―2014年、2015年
石井さん―2009年、2013年
佐藤さん―2014年
吉本さん―2015年
よし子さん―2013年、2014年、2015年
ヴォーヴァ―2015年
著者等紹介
後藤悠樹[ゴトウハルキ]
1985年生まれ。日本写真芸術専門学校卒業。NPO法人日本サハリン協会会員。広告写真家のアシスタント、アパレルカメラマンを経て、写真館勤務。2006年よりライフワークとしてサハリン(樺太)の撮影を始め、定期的に長期滞在を繰り返す。2014年には北海道大学の研究者との共同プロジェクトを発足し、2016年には、その成果物として「サハリン残留 日韓ロ100年にわたる家族の物語」(高文研)を刊行(写真を担当)。2016年よりユーラシア大陸最東端、チュコト半島での撮影プロジェクトを開始(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
宇宙猫
スリカータ
みろみ
きのこスタイル
-

- 和書
- アーリィ・オータム