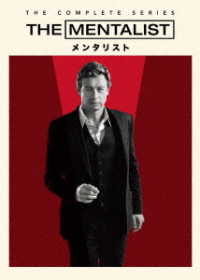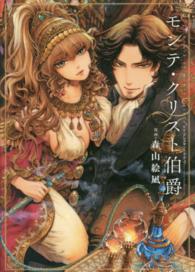出版社内容情報
90年代の後半から始まる人間の心の研究領域の飛躍的な進化──脳の10年──を経て,神経科学は多くの真実を明らかにしてきた。本書は,そこから生まれた対人関係神経生物学をもとに,精神療法(サイコセラピー)のアート(治療技術)の科学性を解き明かし,古典的な心理理論を捉え直し,より科学的な精神療法のあり様を考えたアラン・N・ショアの大作である。
左脳の認知的共感から右脳の身体に基盤を持つ情動的共感へと舵を切ることをショアは求める。ショアは,右脳精神療法,現代アタッチメント理論,神経精神分析,調整理論など刺激的なテーマを思索し続け,実践し続けた。心理学者であり,精神療法の実践者であり,人間の心についての思想家でもあるショアの全貌がこの1冊に込められている。また,訳者による「アラン・ショア著作用語集」も本書には掲載される。本書は多くの臨床家に読んでいただきたい1冊である。
【目次】
内容説明
90年代の後半から始まる人間の心の研究領域の飛躍的な進化―脳の10年―を経て、神経科学は多くの真実を明らかにしてきた。本書は、そこから生まれた対人関係神経生物学をもとに、精神療法(サイコセラピー)のアート(治療技術)の科学性を解き明かし、古典的な心理理論を捉え直し、より科学的な精神療法のあり様を考えたアラン・N・ショアの大作である。左脳の認知的共感から右脳の身体に基盤を持つ情動的共感へと舵を切ることをショアは求める。右脳精神療法、現代アタッチメント理論、神経精神分析、調整理論など刺激的なテーマを思索し続け、実践し続けているショアは、心理学者であり、精神療法の実践者であり、人間の心についての思想家でもある。本書は、そのショアの全貌がまとめられているものである。また、訳者による「アラン・ショア著作用語集」も本書に掲載。多くの臨床家に読んでいただきたい1冊である。
目次
第1部 感情調整療法(ART)と臨床神経精神分析(現代アタッチメント理論―発達と治療における感情調整の中心的役割;関係外傷と発達途上の右脳―精神分析的自己心理学と神経科学の接面;右脳の感情調整―発達、外傷、解離、精神療法の本質的メカニズム;右脳の暗黙的自己は精神分析の核心にある;治療的エナクトメント―右脳の感情耐性の窓での作業)
第2部 発達感情神経科学と発達神経精神医学(アタッチメント、感情調整、発達途上の右脳―発達神経科学と小児科学の連携;ゾウはどのようにドアを開けているか―発達神経行動学、アタッチメント、社会的文脈;アタッチメント外傷と発達途上の右脳―病理的解離の起源;境界性パーソナリティは特に右半球障碍か?―単一試行分析を使用したP3aの研究;ボウルビィの進化的適応環境(EEA)―現在の米国文化の減弱
母子アタッチメント関係の臨床評価を導くための調整理論の使用
家族法とアタッチメントの脳科学―家庭裁判所のレビューでインタビュー)
著者等紹介
ショア,アラン・N.[ショア,アランN.] [Schore,Allan N.]
1943‐。認知心理学者、精神療法家。カルフォルニア州立大学デイビッド・ゲフィン医学部臨床教員。神経科学、精神医学、精神分析学、アタッチメント理論、トラウマ研究、行動生物学、小児科学、臨床心理学、ソーシャルワークなど、多岐にわたる研究と実践を続ける。神経科学とアタッチメント理論を統合した画期的な業績により、彼は「アメリカのボウルビィ」と呼ばれ、感情発達の分野では「右脳がいかに感情を制御し、自己感覚を処理するかについて世界をリードする権威」、そして精神分析学の分野では「神経精神分析学における世界的な第一人者」と評されている。また、「右脳精神療法研究所(Right Brain Psychotherapy Institute)」を設立し、個人精神療法、力動的精神療法、カップルセラピー、身体指向性セラピー、および集団精神療法における、根本的な神経生物学的変化メカニズムへのより深い理解を育むことを目的としている
小林隆児[コバヤシリュウジ]
1949年鳥取県米子市生まれ。児童精神科医、医学博士。1975年九州大学医学部卒業。福岡大学医学部精神医学教室入局後、大分大学、東海大学、大正大学を経て、西南学院大学を70歳で定年退職。その後、感性教育臨床研究所代表として現在に至る。臨床活動は非常勤医師としてクリニックおぐら(東京都世田谷区)にて従事している。専門分野は、乳幼児精神医学、児童青年精神医学、関係発達精神病理学、精神療法。学会活動は、日本児童青年精神医学会理事、日本小児精神神経学会理事、日本小児精神神経学会会長、日本乳幼児医学・心理学会理事長などを歴任。現在は、日本精神神経学会、日本児童青年精神医学会、日本精神分析学会、日本心理臨床学会、World Association for Infant Mental Health(世界乳幼児精神保健学会)に所属。現在、精神疾患理解の脱構築に取り組むとともに、定期的にオンライン形式での感性教育講座を開催して臨床家養成に力を注いでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme