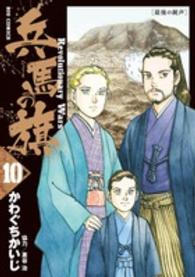- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
目次
山鉾の祭り―その成立と発展(祇園御霊会から祇園祭へ;祇園祭山鉾の形成と発展;山鉾の本質と形態;山鉾の祭り祇園祭;中世的山鉾の祭りとその伝流;小袖の風流;近世都市祭礼と山・鉾・屋台)
折口信夫依代論の原点―髭篭と傘鉾(髭篭依代論;髭篭と出し;だいがく傘鉾論;篭のある傘鉾;だいがくの諸相;太陽神形代解釈の背景)
付録 ユネスコ無形文化遺産登録候補「山・鉾・屋台行事」
著者等紹介
植木行宣[ウエキユキノブ]
1932年生。立命館大学大学院文学研究科日本史学専攻科修士課程修了。文学博士。京都府教育委員会文化財保護課職員を経て、京都学園大学人間文化学部教授となり、文部科学省文化審議会専門委員(文化財分科会第四、第五専門調査会)等を歴任。現在、全国山・鉾・屋台保存連合会、日本工芸会近畿支部顧問等をつとめる
福原敏男[フクハラトシオ]
1957年生。國學院大學大学院文学研究科神道学専攻修士課程修了。論文博士(民俗学)國學院大學。日本女子大学などを経て、現在、武蔵大学教授、國學院大學大学院講師。専攻、日本民俗学・祭礼文化史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tama
5
図書館本 屋台の形の成立に興味あったので。面白くてためになる本ではなく専門家(か、著者の心酔者・縁者)でないと読まないと思う。高齢の専門家が人に読んでもらう気持ちではなく自分の言いたいことを書いたもので、言葉も普通には使わない(お役所用語や法律用語に近い)のをあえて選んでいて物凄く読みにくいし図と文の対応などほぼ考えられてない。筆者はそういう人だから、ここは編集者が何とかするべきなのだろうがなんにもしてない。出版社じゃなくて印刷所なのかな。山口祇園会鷺舞と横須賀三熊野神社の祢里が出てくるので我慢。2016/12/15
ぞくちょう
0
山車まつりに興味があったため手に取ってみた。専門用語が多かったものの知識が入っていればそれなりに読める本(それでも読み飛ばしたところは多々あるが苦笑)。これからの大学の研究のなかでこうしたまつりを扱うことがありそうなので、その時にはまたお世話になるかも。2017/11/15