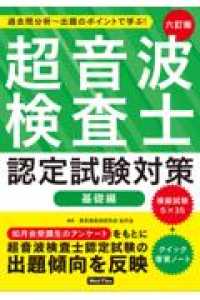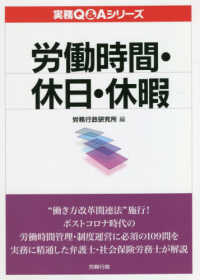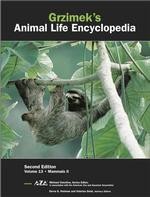内容説明
「フルトヴェングラーとトスカニーニの間に位置する」と評されたその特異な芸風はどのように形成されていったのか―ドイツを中心にヨーロツパやアメリカで活躍したハンガリー出身の指揮者、フェレンツ・フリッチャイ。戦争、音楽界での対立、そして病…多くの困難に直面しながらも、自らが理想とする音楽を追い続け、その中から特異な芸風を創り上げていった名匠の生涯を辿る。
目次
第1章 幼少期から大学卒業まで
第2章 セゲドで指揮者として活動開始、実力を蓄える
第3章 ウィーン客演とザルツブルク音楽祭デビュー
第4章 ベルリン・デビューとRIAS交響楽団首席指揮者就任(第一期ベルリン時代その一)
第5章 RIAS交響楽団を一流オーケストラに(第一期ベルリン時代その二)
第6章 ヒューストン、ミュンヘンでの活動
第7章 晩年(第二期ベルリン時代)
付章 特に忘れ難い演奏
著者等紹介
大脇利雄[オオワキトシオ]
1958年6月、群馬県安中市生まれ。1982年、筑波大学第一学群自然学類(数学主専攻)卒業。同年日本国有鉄道入社、1987年、国鉄分割・民営化に伴い東日本旅客鉄道株式会社に入社、安全対策部門で16年勤めた後、籠原運輸区副区長、安中榛名駅長を歴任。2011年、JR東日本メカトロニクス株式会社に出向、2019年6月、定年で退職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
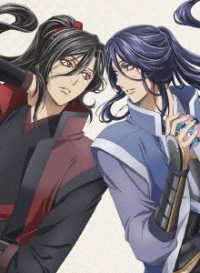
- DVD
- 胡蝶綺 ~若き信長~ 第三巻