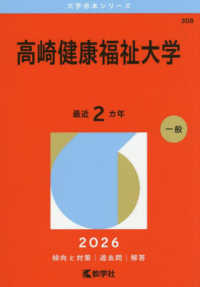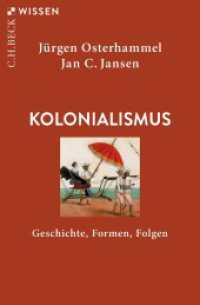出版社内容情報
◆◆AIエージェントと共存、協働していくための必読本◆◆
プログラミングの終わりと新しいエンジニアリングの始まりと言える今、「人類と協働する機械」、AIエージェントをどう捉えて共存していくかを問います。
本書で扱う核心的問いとして次の3つが挙げられます。
「AIによって仕事は奪われるのか」
「AI時代の生産性をどう考えるべきか」
「AI時代に何を作ることが価値になるのか」
前著『エンジニアリング組織論への招待』がブクログ・ビジネス書大賞、翔泳社技術書大賞を受賞した著者と共に本書を通じてAIエージェントの今後を見通します。
■対象読者
本書では次のような方々を主な対象読者として想定しています。
(1) AIを日常業務に活用しているが、「便利さ」以上の成果を実感できていないエンジニア
(2) AIによる生産性向上や組織変革の可能性と課題を理解したいエンジニア/マネージャー
(3) 「AI疲れ」を感じつつも、より良い使い方や未来志向の視点を模索しているエンジニア
(4) これからの社会における“正しいAIとの付き合い方”にヒントを得たいエンジニア
■本書「まえがき」より
「プログラミングは手段である」。この言葉を聞くたびに私の中でモヤモヤとした感情が湧き上がります。なぜなら、私たちエンジニアはその「手段」と呼ばれるものにとことんこだわってきたからです。
それに集中し、肯定してきたからこそ、何か価値あるものを生み出せると信じてきました。コードへの純粋な愛情と探求心こそが、イノベーションの源泉だったのです。
しかし今、AIエージェントの登場により、プログラミングがより純粋に「手段」として機能する時代が到来しています。この変革は、私たちのアイデンティティを根底から揺さぶります。同時に、凄まじい革命によって仕事が劇的に効率化され、創造性がかつてない形で解放される可能性も秘めています。この不安と期待が混在する感覚は、まさに歴史の転換点に立つ者だけが味わう特別な経験なのかもしれません。
私たちは今、どのような姿勢で大きな変化に臨むべきか。
これまでの成功体験をいかにアンラーニングし、新たなクリエイティビティの在り方を見出すか。そして、どのような価値創造が求められるのか。来るべきAIエージェント社会について考えていきたいと思います。
本書を読んで皆様が、プログラミングへの愛と不安両方を抱きながら、AIエージェント時代を切り開いていくこと願っています。
(本書まえがきより抜粋・編集)
【目次】
序章 プログラミングの終わりと新しいエンジニアリングの始まり
第1部 AIエージェントの登場をどう捉えるか
第1章 AIエージェントは世界を食べ尽くす
第2章 コーディングエージェントとバイブコーディング
第3章 私たちの仕事が奪われるのか
第4章 仕事の二極化とジョブレス・リカバリー
第5章 日本特有の課題と機会
第2部 人と半導体の新しい組織論
第6章 文字の発明とソフトウェア
第7章 人と半導体の価値転換
第8章 意思決定の高密度化とAI疲れ
第9章 正しさの転換とAI活用の5段階
第3部 知識創造というソフトウェアの新大陸
第10章 拡張を続けるシステム領域
第11章 SECIモデルとAIエージェントの統合
第12章 知識創造エージェントの企業戦略
第4部 AIと協働する未来を生き抜く
第13章 赤の女王と相対優位の原則
第14章 個人のサバイバル戦略
第15章 経営のコミットメントと消える生産性
第16章 両利きの経営とエフェクチュエーション
終章 本能を信じて走り続ける者が未来をつくる
内容説明
人が直接コードを書く時代は終わり、新たなエンジニアリングの地平が開かれようとしています。「人類と協働する機械」―AIエージェントとは何か。私たちはその知性とどう向き合い、どのように共存していくのか。本書は、その根源的な問いに挑みます。「AIは人の仕事を奪うのか?」「AI時代の生産性とは何か?」「そして、何を創ることが人間の価値となるのか?」AIとともに歩む未来、その最初の一歩をこの一冊からはじめてください。
目次
序章 プログラミングの終わりと新しいエンジニアリングの始まり
第1部 AIエージェントの登場をどう捉えるか(AIエージェントは世界を食べ尽くす;コーディングエージェントとバイブコーディング;私たちの仕事は奪われるのか;仕事の二極化とジョブレス・リカバリー;日本特有の課題と機会)
第2部 人と半導体の新しい組織論(文字の発明とソフトウェア;人と半導体の価値転換;意思決定の高密度化とAI疲れ;正しさの転換とAIエージェント成熟度)
第3部 知識創造というソフトウェアの新大陸(拡張を続けるシステム領域;SECIモデルとAIエージェントの統合;知識創造エージェントの企業戦略)
第4部 AIと協働する未来を生き抜く(赤の女王と相対優位の原則;個人のサバイバル戦略;AIエージェント経営と4つの壁;両利きの経営とエフェクチュエーション)
終章 直観を信じて行動する
付録
著者等紹介
広木大地[ヒロキダイチ]
株式会社レクター代表取締役。1983年生まれ。筑波大学大学院を卒業後、2008年に新卒第1期として株式会社ミクシィに入社。同社のアーキテクトとして、技術戦略から組織構築などに携わる。同社メディア開発部長、開発部部長、サービス本部長執行役員を務めた後、2015年退社。現在は、株式会社レクターを創業し、技術と経営をつなぐ技術組織のアドバイザリーとして、多数の会社の経営支援を行っている。著書『エンジニアリング組織論への招待~不確実性に向き合う思考と組織のリファクタング』(技術評論社、2018年)が第6回ブクログ大賞・ビジネス書部門大賞、翔泳社ITエンジニアに読んでほしい技術書大賞2019・技術書大賞受賞。一般社団法人日本CTO協会理事。朝日新聞社社外CTO(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
monotony
キウイ好き
-
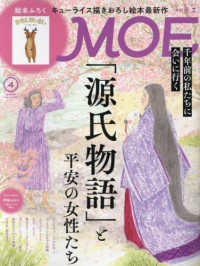
- 和雑誌
- MOE (2024年4月号)