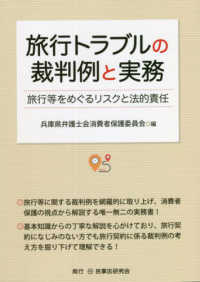出版社内容情報
大事な部分は聴いて頭に入れることができる!「聴く」ことから「思考力」が身につく!よく聴いて思考の流れを知る「思考の整理学」。
「聴く」ことから「思考する力」が身につく!
「聴く」と「聞く」。「聴く」は注意深く聴くことで、単なる聞こえることとは違う。注意して聴きつづけることはかなり疲れるため、講演会でもつい居眠りしてしまう人は多い。大事なことを聴いて頭に入れる力が弱っているのである。思考の流れについていくのが下手な人が多い日本は、「耳バカ社会」になっている。
知性とは「聴く」「話す」「読む」「書く」の4つがすべて揃って養われる。「読む」「書く」が重視されている現代だが、「聴く力」=人の話をよく聴くことから「思考力」が深まっていく。
思考力の方法としての「聴く力」について考える。
?T 耳バカ社会
?U 基本は「聴く話す」
?V 「読む書く」重視の欠陥
?W 日本語の大問題
?X 知は「聴く話す」「読む書く」生活から
【著者紹介】
1923年、愛知県に生まれる。英文学者、評論家、エッセイスト。お茶の水女子大学名誉教授、文学博士。東京文理科大学英文科卒業後、雑誌「英語青年」編集、東京教育大学助教授、お茶の水女子大学教授、昭和女子大学教授を歴任。専門の英文学をはじめ、言語論、教育論など広範囲にわたり独創的な仕事を続ける。著書にはミリオンセラーとなった『思考の整理学』(ちくま文庫)をはじめ、『「マイナス」のプラス-反常識の人生論』(講談社)、『「人生二毛作」のすすめ』(飛鳥新社)、『失敗の効用』(みすず書房)、『思考力』(さくら舎)、『乱読のセレンディピティ』(扶桑社)、『老いの整理学』(扶桑社新書)、『外山滋比古著作集』(全8巻、みすず書房)などがある。
内容説明
大事な部分は聴いて頭に入れる!よく聴いて思考の流れを知る「思考の整理学」!!“知の巨人”が明かす「聴く」ことから「思考する力」が身につく法。
目次
1 「聴く」が聡明のはじまり(講演は聴くべきもの;耳バカ社会;消えた“耳学問” ほか)
2 思考を深める「聴く話す」(「読む書く」の前に「聴く話す」;耳のことばが思考を支える;四十ヵ条の暗黒 ほか)
3 「読む書く」重視の落とし穴(音読と黙読;日本語の難点;既知の読み、未知の読み ほか)
4 日本語の大問題(ことばの距離感覚;向き合いたくない;悪魔のことば ほか)
5 知となる「聴く話す」(ことばの西高東低;思考を生むもの;耳が弱いと困ったことに ほか)
著者等紹介
外山滋比古[トヤマシゲヒコ]
1923年、愛知県に生まれる。英文学者、評論家、エッセイスト。お茶の水女子大学名誉教授、文学博士。東京文理科大学英文科卒業後、雑誌「英語青年」編集、東京教育大学助教授、お茶の水女子大学教授、昭和女子大学教授を歴任。専門の英文学をはじめ、言語論、教育論など広範囲にわたり独創的な仕事を続ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
mari
bros
のぶのぶ
Squirrel