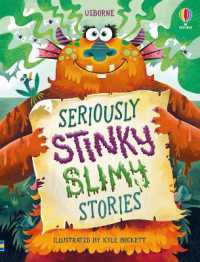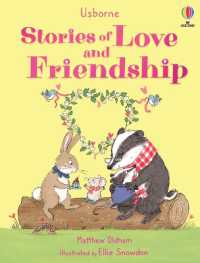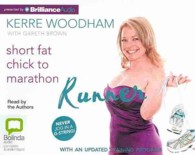出版社内容情報
「社会運動」か、「国家」の再評価か?
グローバリズムに対するブルデューの「回答」の核心を明かす!
1960年代の活動当初から社会に介入=発言し続ける「知識人」であったブルデューの真価とは何だったのか。冷戦終結を経て、20世紀型知識人が有効性を失っていく今、全生涯の社会的発言を集成し、旧来型の「社会運動」への挺身でも「国家」の単純な再評価でもなく、その両者を乗り越えてグローバリズムの対峙したブルデュー思想の現代的意味を炙り出す、決定版論集。
【著者紹介】
●ピエール・ブルデュー(Pierre Bourdieu, 1930-2002)高等師範学校卒業後、哲学の教授資格を取得、リセの教員となるが、55年アルジェリア戦争に徴兵。アルジェ大学助手、パリ大学助手、リール大学助教授を経て、64年、社会科学高等研究院教授。教育・文化社会学センター(現在のヨーロッパ社会学センター)を主宰し学際的共同研究を展開。81年コレージュ・ド・フランス教授。主著『ディスタンクシオン』『再生産』『芸術の規則』『パスカル的省察』『科学の科学』『自己分析』『国家貴族』(以上邦訳、藤原書店)ほか多数。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
26
2002年初出。完全雇用社会。失業と排除に対して、労働時間短縮でどう闘うべきか? 平等と連帯を保証し、市民に身近で雇用を創出する公共サーヴィスはいかにあるべきか? (462頁)などの問いは、日本でも極めて重要な論点。失業者の運動が善良な貧困者と悪い貧困者、排除された人びとと失業者、失業者と給与生活者の間の、体系的に維持されている分断に異議を申し立てたこと(480頁)。文化資本の普及は、象徴的なものの領域における歴史的に不可逆的な変化であり、2016/06/24
roughfractus02
8
60年代のアルジェリアから5月革命を経て科学(学問)が非政治化し、科学(学問)も専門化を徹底して物理数学科学を導入した「科学」と化し、教育の領域から玄人と素人の差別化が進んでエリートの再生産する社会を強化する。40年に渡る著者の政治的発言を辿るとフランスのみならず、20世紀後半からグローバル化する世界が類似の動向にあったように思えてくる。一方そのつどの発言からは、著者は一瞬ごとに変わりうる振る舞いや文体がある性向を作りつつある力の場を分析対象としながらその可変的な場に自ら参入して発言してきたことがわかる。2024/06/04
-

- 電子書籍
- 気候変動規範と国際エネルギーレジーム …