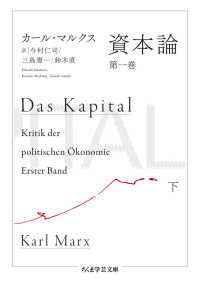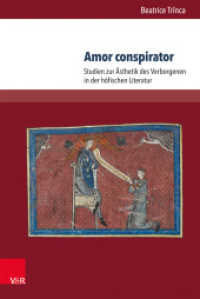目次
はじめに―千人にひとりの落ちこぼれ、未来の学校づくりを考える
第1章 「みんなの学校」の衝撃
第2章 杉並の地域づくり・学校づくり
第3章 N高の挑戦
第4章 侍学園という希望
第5章 大槌の教育復興
鈴木敏夫・税所篤快対談―鈴木敏夫さんと語る、2030年の才能の育て方、学びのゆくえ
著者等紹介
税所篤快[サイショアツヨシ]
国際教育支援NPO e‐Education創業者。1989年生まれ、東京都足立区出身。早稲田大学教育学部卒業、英ロンドン大学教育研究所(IOE)準修士。19歳でバングラデシュへ。同国初の映像教育であるe‐Educationプロジェクトを立ち上げ、最貧の村から国内最高峰ダッカ大学に10年連続で合格者を輩出する。同モデルは米国・世界銀行のイノベーション・コンペティションで最優秀賞を受賞。五大陸ドラゴン桜を掲げ、14ヵ国で活動。未承認国家ソマリランドでは過激派青年の暗殺予告を受け、ロンドンへ亡命。現在、リクルートマーケティングパートナーズに勤務、スタディサプリに参画(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ta_chanko
12
大空小学校・N高・侍学園・大槌町の、新しい教育への取り組み。いずれも常識にとらわれず、「わくわくする学び」を大切にしながら、地域やさまざまな人々と協働して子どもたち一人一人の感性や経験を育んでいく。画一的な一斉授業のスタイルは、時代遅れの工業化モデル。もっと多種多様な学びがあってよい。文科省の履修絶対主義も何とかならないものか。時代に合った学びのかたちを、それぞれの場所で追い求め、刺激し合うことでより良いものをつくっていけるとよい。2020/08/09
Shori
5
「未来の学校のつくりかた」の答えを導く本ではない。 自分はこれから、子どもに、学校に、地域に何ができるだろう。ワクワクが自然と沸き上がる本だった。 日本にはこんなにおもしろい現場がある。 理想の学校や教育は探して見つけるものではなく、子どもや教職員、地域とともにつくりあげるもの。 好奇心に溢れ、挑戦を厭わない大人こそ、「子どものやる気の発火点」をつくることができる。 著者自身のように、自身もそう在り続けたいと強く思わせてくれた、大切な一冊です。 2020/06/06
Yuka
4
教育についての知識がだいぶ古くなって来ているのでアップデート。大空小とかN高とか今話題の学校が取りげられている。サムライ学園とか全く知らないものもあって面白かった!共通してるのはどこもゼロorリセットでスタートできている点で、既存の教育現場から地域を生かした取り組みにするには杉並のようにかなり強いリーダーシップと長期の時間が必要なのでは。事例として参考になるのは杉並だけかなぁと思うけど、ぶれないリーダーシップのある人が全ての地域にいるわけもなく…良い人が居るかで教育の質が変わってしまうのかなぁと思った。2021/03/03
ぼっち
4
様々な先進的な学校について学べました。まちづくりとは人づくりであり、人づくりとは教育である。つまりはその教育の場となる学校が地域の人と一緒に機能してこそ本来の価値が出てくるのではないか、そんなことを事例を持って伝えてくれます。2030年には学校も地域の存在もどうなっているかわからないですが、いま日本にとって大事な教育の在り方を見直すとても貴重な一冊だと思いました。大槌町のストーリーは胸が熱くなりうるっときてしまいました。いい話で終わらせず、自分の地域にも活かしていきたいと思います。2020/09/06
かりん
4
5:《未来の学校へのワクワクが伝播する。》著者と苫野さんのオンライントークをきっかけに興味を持ち購入。苫野さんが言っていた通り、税所さんの「おら、ワクワクすっぞ!」という雰囲気が読者にも伝わってくる。個人的には、N高についてよく知らなかったので特に驚きが多く、刺激を受けまくる。大空小はさらに知りたくなったが、映画を見たある先生が言っていた言葉に同意で、「自分もこうやってみたい!」と思える体力がない…。総じて、生徒第一という当たり前だが難しいことにとことん向き合っている5つの事例でした。E2020/07/12
-
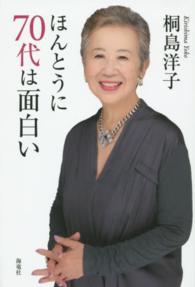
- 和書
- ほんとうに70代は面白い