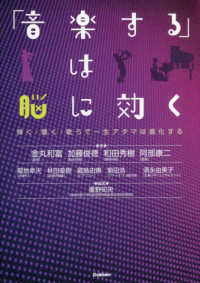感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
24
クラシックオタク2人の雑談を聞くような軽いノリの一冊。平成の始まりは劇的。1989年のニューイヤーコンサートはカルロス・クライバーだった!。7月にカラヤンが亡くなり、12月にバーンスタインの壁崩壊の第九。平成2年にバーンスタインが没し、クーベリックの「わが祖国」の凱旋。それに比べて後の30年間は冴えなかったなあという印象。平成に大流行した古楽器運動を「音楽の歴史に対する反動」と断じるロストロポーヴィチの気持ちもわかる。二人の無責任な発言が面白い:「プーチンとゲルギエフ、宇野功芳と司馬遼太郎が似ている」?!2019/06/16
しーふぉ
22
テレビ番組の対談が基になっているようです。クラシックの世界の平成の動きを小澤征爾や佐村河内までフランクに語り合っている。佐村河内のゴーストライターの新垣のことは、彼は職人なんです。自分がやりたいことではなくオファーされたことをやるのが上手。中身は最後はマラーのそのまんま。みたいなことが書いてあって、クラシックの世界ではそういう認識なんですね。2019/06/09
無重力蜜柑
11
最近音楽に興味が出ている。そういえば片山杜秀は音楽評論もやっていたな……と思い読んだ。まさかこのタイトルでクラシック音楽のみに焦点を当てているとは。でも予想外に面白かった。クラシックについての知識が全然なくても、何を言っているか全然分からなくても楽しめる。要はオタクのおっさん達が無限にオタク語りするだけの本なのだが、彼らの異常な熱量と知識量だけで愉快になれてしまうのだ。あれもこれもと結びつけて珍妙な星座を描いてしまう手つきと、その奇妙な説得力。優れたオタクってのはどの分野でも変わらないんだなと実感する。2025/12/03
izw
8
2018年8月19日に放送された片山杜秀と山崎浩太郎の対談が元になっている。時代を語るには10年単位では短すぎる、50年、100年ではその年代を通して体験した人が少ない。平成は、長さとしても丁度よく、ベルリンの壁崩壊の年から始まり、日本だけでなく世界の歴史の区切りとなる重要な30年間だった。その中で、クラシック音楽の変遷について語る二人の造形の深さに感服する。阪神大震災、サリン事件、東日本大震災、佐村河内事件と平成に起こった大事件に関わるトークを通じてクラシック音楽の変遷がよく分かる。2019/09/15
Susumu Kobayashi
7
衛星デジタル音楽放送「ミュージックバード」の121チャンネル、「ザ・クラシック」で放送された4時間番組を基にして構成された本とのこと。平成という時代の日本および世界における音楽をたどっている。片山:「作曲家の箕作秋吉が戦前に書いていますが、アマチュアのピアニストのベートーヴェンやショパンは聴いていられないのに対して、大学のアマチュア・オーケストラの弦楽合奏はそれと同じくらいかもっと下手なのに、不思議と音楽として聴いていられると」(p. 62)。確かにそうだ。古書山たかし氏がどのような感想を抱くか興味津々。2019/08/04