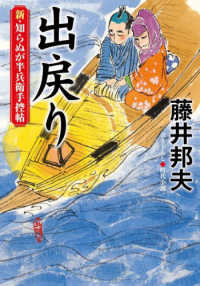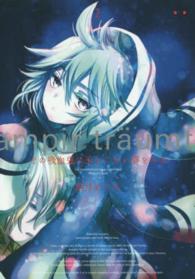出版社内容情報
青森、秋田、東京から徳島、奄美、沖縄まで、写真家と追いかけた全国13の祭り探訪記。祭りの中で見つけたもうひとつの日本!青森、秋田、東京から徳島、奄美、沖縄まで、
写真家と追いかけた全国13の祭り探訪記。
祭りの中で見つけたもうひとつの日本!
「祭りと盆踊りと出会う旅とは、僕にとってはそれまでまったく知らなかった日本列島の姿を発見する旅でもあった」(あとがきより)
2010年の夏、「高円寺阿波おどり」と「錦糸町河内音頭大盆踊り」に衝撃を受けた著者は、以来南米のカーニバルやレイヴ・パーティーにも通じる祝祭感、高揚感のなかに、いまだ見知らぬ列島の姿を求めて、日本各地の祭りを追いかけている。本書にはそんな旅のなかから、北は青森、秋田、南は奄美、沖縄まで、全国13の盆踊り・祭り体験を臨場感あふれる写真とともにお楽しみください。
【著者が訪ねた盆踊り・祭り】
大川平の荒馬踊り(青森県)
五所川原立佞武多(青森県)
西馬音内盆踊り(秋田県)
秩父夜祭(埼玉県)
錦糸町河内音頭大盆踊り(東京都)
高円寺阿波おどり(東京都)
郡上おどり&白鳥おどり(岐阜県)
磯部の御神田(三重県)
阿波おどり(徳島県)
香春町の盆踊り(福岡県)
牛深ハイヤ節(熊本県)
奄美大島のアラセツ行事と八月踊り(鹿児島県)
市来の七夕踊(鹿児島県)
本島と浜比嘉島のエイサー(沖縄県)などなど
はじめに
1 下町に鳴り続ける不死のリズム──東京・錦糸町河内音頭大盆踊り
2 クールな囃子に揺れる東北のゴースト・ダンス──秋田・西馬音内盆踊り
3 死の記憶が刻み込まれた盆踊りのステップ──岐阜・郡上おどり&白鳥おどり
4 リズムに熱狂する〈ねぶたの国〉の短い夏──青森・大川平の荒馬踊りと五所川原立佞武多
5 霊山の麓を揺るがす屋台囃子のハートビート──埼玉・秩父夜祭
6 神話的世界で繰り広げられる伊勢の田園エンタテインメント──三重・磯部の御神田(おみた)
7 日本最強のダンス・ミュージックが生み出す祝祭空間──東京・高円寺阿波おどり
8 海を渡った〈踊る阿呆〉のDNA──徳島阿波おどり?熊本・牛深ハイヤ節(前編)
9 天草の〈風待ちの港〉で阿波おどりのルーツと出会う──徳島・阿波おどり?熊本・牛深ハイヤ節(後編)
10 南西諸島とヤマトの交流が育んだルーツ・リズム──鹿児島・奄美大島のアラセツ行事と八月踊り
11 沖縄の夏の風物詩に念仏踊りの影を見る──沖縄・本島と浜比嘉島のエイサー
12 炭坑の町で盆踊りの原風景に触れる──福岡・香春町の盆踊り
14 異人やケモノも登場する農村の一大スペクタクル──鹿児島・市来の七夕踊
あとがき
[コラム]
・〈未来の音頭〉を夢見るイノヴェイターたち 河内音頭・歴史編
・目指すところは〈踊れる話芸〉 世界で唯一人のプロ河内音頭ギタリスト、石田雄一さんに聞く
・更新され続ける〈伝統〉 ?東京音頭?以降の新作音頭が鳴り響く現代の盆踊り
・祭りの起源と目的 神事としての祭りにリズムを見出す
・阿波おどりは音楽以上の何か、太鼓は楽器以上の何か 東京天水連お囃子部長・上山孝司さんに聞く
・それでも祭りを続けるのか? 現代の祭りを取り巻くさまざまな問題と課題
大石 始[オオイシハジメ]
1975年、東京生まれ。ライター、編集者。雑誌編集者を経て、2008年からフリーランスとしてワールドミュージックや民族音楽/芸能の取材記事、旅の紀行文などを各媒体に寄稿。これまでの著書に2015年の『ニッポン大音頭時代 「東京音頭」から始まる流行音楽のかたち』、2010年の『関東ラガマフィン』、編著書に2014年の『大韓ロック探訪記』、共同監修を手がけた書籍に『GLOCAL BEATS』(2011年)などがある。旅と祭りの編集プロダクション「B.O.N」所属。
ケイコ・K・オオイシ[ケイコケイオオイシ]
1974年、東京生まれ。フォトグラファー、デザイナー。各媒体に写真を提供するほか、デザイナーとしてディスクガイド・ブックやアパレルなど各種広告、イヴェント・フライヤーを手掛ける。2012年にはコンピレーション・アルバム『DISCOVER NEW JAPAN 民謡ニューウェーブ VOL.1』のアートワークを手掛けた。旅と祭りの編集プロダクション「B.O.N」所属。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
華形 満
yone
Natsuhiko Shimanouchi
KakeruA
-

- 電子書籍
- 俺だけ偉人ガチャ回せて最強の世界【タテ…
-
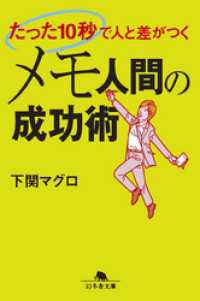
- 電子書籍
- たった10秒で人と差がつく メモ人間の…