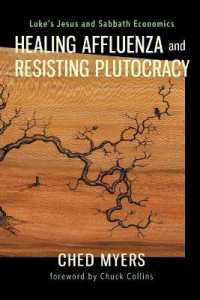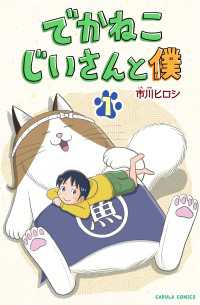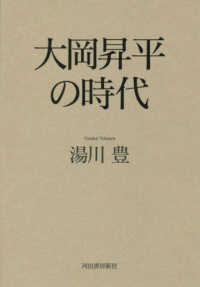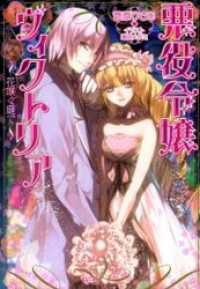出版社内容情報
交響曲はなぜ偉大で崇高なのか?
音楽を聴くことはいつから真理の探究と等しい行為になったのか?──
1800年をまたぐ数十年間に、人々はそれまでとは違うやり方で音楽を聴き始める。
器楽曲は思想を伝え、真理を告げ、理想の国家を表象する媒体となった。
美学上の革命と社会革命とが合流を遂げたこの時代、聴衆の〈耳〉は交響曲に何を聴くようになったのか──。
ベートーヴェン時代の人々の感性に大胆にアプローチした画期的な音楽論。
現在もっとも注目を集める音楽学者ボンズの主著Music as Thought(2006)を、日本を代表する作曲家と気鋭の音楽学者が翻訳。
プロフィール
マーク・エヴァン・ボンズ(Mark Evan Bonds)
ノースカロライナ大学チャペル・ヒル校教授(音楽学)。アメリカおよびドイツの大学で学び、ハーヴァード大学で「ハイドンの偽再現部と18世紀におけるソナタ形式の知覚」により博士号。主な研究分野は、古典派およびロマン派の音楽(とくに器楽)の歴史と、それにかかわる思想。多くの著書があり、近著には、『絶対音楽』(2014)、『西洋音楽史』(2003)など。また、学術誌『ベートーヴェン・フォーラム』の編集主幹も務めた。
近藤譲(こんどう・じょう)
作曲家。お茶の水女子大学名誉教授。アメリカ芸術・文学アカデミー外国人名誉会員。作曲とともに、活発な執筆活動を展開。主著に『線の音楽』『聴く人(homo audiens)』(以上、アルテスパブリッシング)、『音を投げる』『〈音楽〉という謎』(以上、春秋社)、『耳の思考』(青土社)など。また、主な訳書に、ヒューズ『ヨーロッパ音楽の歴史』(共訳)、ケージ『音楽の零度』(編訳)(以上、朝日出版社)など。
井上登喜子(いのうえ・ときこ)
お茶の水女子大学助教(音楽学)。お茶の水女子大学で学び、同校で「19世紀ドレースデンの合唱協会の社会史研究」により博士号。東邦音楽大学准教授を経て現職。主な研究分野は、19世紀ドイツの音楽社会史および近代日本の西洋音楽受容史。近年の論文としては、「戦前日本におけるオーケストラの曲目選択に関する実証研究」など。
CONTENTS
序
プロローグ 思いがけない曲種──交響曲の興隆
第一章 想像力をもって聴くこと──美的関心の革命的変化
カントからホフマンへ
観念論、そして、知覚についての知覚の変化
観念論と聴取の新たな美学
第二章 思考としての聴取──修辞学から哲学へ
修辞学的枠組みにおける聴取
哲学的枠組みにおける聴取
哲学としての芸術
第三章 真理を聴く──ベートーヴェンの第五交響曲
無限なる崇高
認識としての歴史
意識と無意識の統合
有機的まとまり
崇高なるものを超えて
第四章 美的国家を聴く──コスモポリタニズム
交響曲、共同体の声
個人と社会の統合:差し迫った要求
有機的組織体としての国家
シラーの美的国家の思想
ゲーテの教育州
第五章 ドイツ国家を聴く──ナショナリズム
ドイツ・ナショナリズム
「ドイツ的な」曲種としての交響曲
音楽祭:演奏のポリティックス
民主制としての交響曲
エピローグ 形式を聴く──絶対音楽という避難所
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さえきかずひこ
植岡藍
z