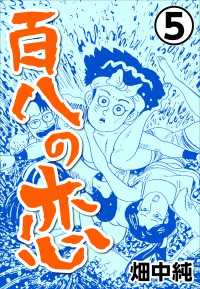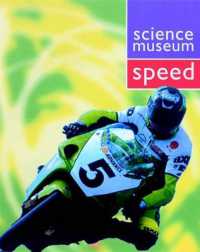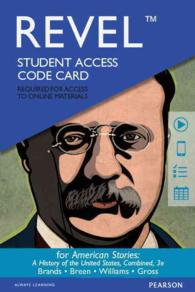出版社内容情報
特長1.大学入試改革でも求められる「思考力・判断力・表現力」を伸ばす
TOK(Theory of Knowledge:知の理論)は、IB(国際バカロレア)のディプロマプログラムにおいて中核となる学習の一つで、Critical Thinking(批判的思考)を体系的に培う学習として広く注目されています。
本書は、TOK導入用の学生向け解説書“Decoding Theory of Knowledge”の翻訳書です。豊富なケーススタディにより、大学入試改革でも求められる「現行の教科・科目の枠を超えた『思考力・判断力・表現力』」を伸ばします。
特長2.実社会の状況に即した豊富な課題
各章の課題は、批判的思考力や分析力を磨くことを目的として設定されており、高校生にもわかりやすい身近なトピックで導入を行います。
Real-life situation欄では実社会の状況を紹介することで、学習者がより一層思考し、探究するきっかけを与えます。
特長3.プレゼンテーションやエッセイでのアウトプット
本書では、分析や研究、議論を通して、さまざまなものの見方を認識して理解します。
また、プレゼンテーションを上手に計画・実施したり、エッセイの質を高めるための説明や評価基準が掲載されています。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
柳田
12
授業で読んだのだが、書誌情報がなくこれであっているかどうか不明。読んだのは多分本編なのでちがうがこれしか出てこない。国際バカロレアのカリキュラムの一部の「知の理論」である。暗記の必要のない教科書だから易しく、1時間半くらいで読めた。基本的に高校生向けだが、よくできていると思った。大学入学のための資格試験だから、まあ当たり前なのだが、特に文系のアカデミックスキルズの基本をおさえるという感じで、日本の大学の初年度教育は先生によってまちまちだし、こういうのやったらいいと思った。ちょっと人文系に偏りがある印象。2018/06/24
isao_key
6
本書はTOK(知の理論)に関するプログラムについてIB(国際バカロレア)の指導書である。暗記中心の詰め込み式の教育とは異なり、批判的思考や分析力を身につけることを念頭に置いている。ここで議論されている内容についても、知識とは何か、知識に関する問いとは何か、など根源的な哲学的問いかけもある。例えば「私たちは言い表すための言葉や言語がなくても、何かを知ることができるならば、何かを知ることができるのでしょうか。もし私たちに話す能力があり、流ちょうに話すことができるならば、知識が豊富だとみなされるのでしょうか。」2018/10/09
野村一夫:秘伝のタレは2度捨てろ
1
国際バカロレア試験の中心的科目「知の理論」のテキスト。サブゼミの1つでこれをやっているが、知識全般への話の糸口にはなる。基本的に大学受験参考書で、目標は比較的長い作文を書くことで、後半は小論文の書き方に充てられる。あくまで教育的なものなので内容は雑である。やはり本家フランスのバカロレアの「哲学」に立ち戻るべきだと思う。ちくま学芸文庫にフルキエの『哲学講義』全4冊がある。ヴェルジェスとユイスマンの『哲学教程』全2冊も筑摩書房から出ている。哲学史ではなく人生を考える哲学である。日本の高校倫社の教科書と真逆だ。2019/12/01
ざっきい
1
ふと目につき読んだ本。本書でいうTOK(知の理論)とは、国際バカロレア・ディプロマプログラムという16〜19歳を対象としたカリキュラムの必修科目で、知識とは何かといった問いを元に批判的思考ができるツールを提供するものである。似非科学、トンデモ、科学哲学など興味があれば、本書の前半部がよくまとめられたツールボックスになっていると考えるだろう。個人的には、これを16歳から学べる者がいる、ということに驚かざるをえない。2019/04/21
pinkie
0
知識を身につけるだけではなくて、それを使って「何ができるようになるか」を明確にしていくことがこれからの教育に求められています。でも知識を使う、使い方を教えるためには、前段階として「知識とはそもそも何なのか」を分かっていないといけないのではなかろうか。読みながらそんなことを考えました。TOKの評価課題に関するパートは具体的で参考になったしTOK以外にも援用できそう、と思ったけれど、肝心の「TOKとは何か」は分かったような分からんような…… また読み返そう。2017/12/21