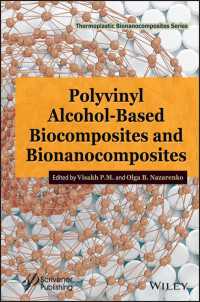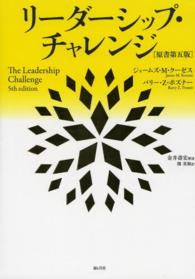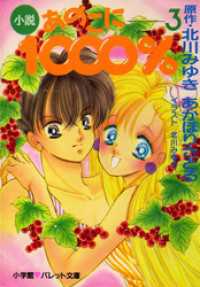内容説明
食の歴史を知るとゾラの読み方が、ミレー、ゴッホの見方が変わる。食材や調理方法を絶え間なく変化させ続けてきたフランス人たちの食事に対する飽くなき関心、食文化から文学・芸術を読み解く。
目次
1 フランス料理からフランス美食学へ(料理とは何か、あるいは自然と文化;スパイスの料理 ほか)
2 アントルメとパティスリー(蜂蜜から砂糖へ;メとアントルメ ほか)
3 パンの歴史とフランス人(パンを食べる人、粥を食べる人;皿としてのパン ほか)
4 ジャガイモとフランス(ジャガイモと飢饉;フランスのジャガイモ受容 ほか)
5 ワインとアイデンティティー(レストラン・ビストロ・ブラッスリー;古代におけるビール ほか)
著者等紹介
武末祐子[タケマツユウコ]
西南学院大学外国語学部教授。グルノーブル第三大学フランス文学博士DSR取得。パリ第四大学フランス文学DEA取得。専門は一九世紀フランス文学、研究テーマは文学・芸術におけるグロテスク美学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Go Extreme
2
「料理は自然と文化の媒介」レヴィ=ストロースの料理三角形を通した文化的食物への変容 「美味しくしようとする意志-栄養摂取を超えた文化的行為としての料理 「食卓は舞台」17世紀以降のサービス構成と視覚的美意識の確立 「ガストロノミー=文化そのもの」 食を核とした総合的文化概念 「飢饉を救う貧者のパン」ジャガイモが担った歴史的役割 「地のリンゴ」ジャガイモの文化的受容を象徴する言語戦略 「テロワール=土地の魂」ワインが体現する地域アイデンティティ 「ガストロノミーの総合史」美術・文学・社会史が交差する食の全景2025/04/02
dexter4620
0
フランスの食文化の論文数稿をまとめた一冊。フランス料理を食べるためのトリビアや食材などの歴史を解説。パンやじゃがいも、まずは庶民的なフランス料理が食べたくなってしまいました。2025/09/24