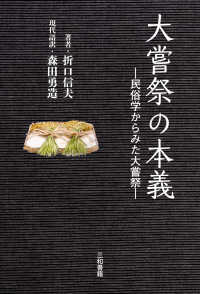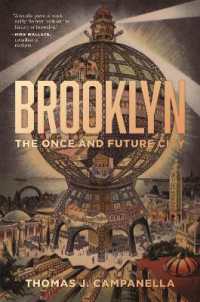- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学その他
内容説明
常設展の見方、作品の背景、収集の哲学…学芸員の「じまん話」がっつり聞いてみた。
目次
1 東京国立博物館―お話 竹之内勝典さん、伊藤信二さん、河野正訓さん/スペシャルゲスト 和田ラヂヲ先生
2 東京都現代美術館―お話 水田有子さん
3 横浜美術館―お話 大澤紗蓉子さん
4 アーティゾン美術館―お話 島本英明さん
5 東京国立近代美術館―お話 成相肇さん
6 群馬県立館林美術館―お話 松下和美さん
7 大原美術館―お話 吉川あゆみさん
8 DIC川村記念美術館―お話 前田希世子さん、中村萌恵さん、海谷紀衣さん
9 青森県立美術館―お話 工藤健志さん
10 富山県美術館―お話 麻生恵子さん、稲塚展子さん、八木宏昌さん
11 ポーラ美術館―お話 工藤弘二さん
12 国立西洋美術館―お話 新藤淳さん、山枡あおいさん
著者等紹介
奥野武範[オクノタケノリ]
1976年、群馬県生まれ。編集者。早稲田大学政治経済学部卒業。株式会社宝島社にて雑誌編集者として勤務後、2005年に東京糸井重里事務所(当時。現在の株式会社ほぼ日)に入社。2023年で創刊25年、毎日更新を続けるウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」の編集部に所属(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひと
29
全国の美術館・博物館の常設展やコレクション展を、各館の学芸員さんの説明を聞きながら回る企画、とても贅沢ですね。解説している作品のすべての画像が示されているわけではなく、掲載されていても画像が小さいのは、現地を訪れて本物を体験してほしいというメッセージなのでしょうね。各館設立の背景や思い入れ、コレクションの方針など、皆個性的。DIC川村記念美術館休館の前に、必ず訪れておかなければと思いました。本書を片手に回るには厚過ぎるので、ネット記事を参照しながら鑑賞してみようと思います。もっとアートと仲良くなりたい。2024/12/05
bluelotus
9
★★★★☆ もっと写真があれば説明されている作品の理解が深まるのになぁと残念に思ったが、気になったら常設展にGo!ということか!(笑)一番最初の東京国立博物館がとにかく面白すぎたし、どの学芸員さんも作品への愛に溢れていた(笑)いつかまたじっくり読んでみたい。2024/05/20
takakomama
8
全国の12のミュージアムの常設展、所蔵作品の取材。行ってないのは東京都現代美術館、青森県立美術館、富山県美術館の3つですが・・・ お目当ての企画展を観て、へとへとに疲れてしまって、常設展は観なかったり、さらっと見るだけなのはもったいない。解説している学芸員さんたちの地元や地元出身者、芸術家、作品への情熱と愛をひしひしと感じます。定点観測のように常設展を観ると、同じ作品でも新しい発見があったり、私の知識が増えていることを実感できて楽しいです。2024/06/21
ナナシ
7
様々な美術館、私はついつい特別展がある時にしか行かないがその美術館の要は何といっても常設展であるということを改めて思い知った。 学芸員の方のこだわりや美術品の見方など、知れば知るほど実際に見て訪ねてみたくなるお話ばかり。対話式なので読みやすい。そして、刀剣乱舞を嗜む審神者達にはトーハクという言葉は耳慣れたものだろうがその東京国立博物館はこの本のトップバッターであり、なんか…ゆるい笑 そのお陰で肩肘張らずに楽しく読めた笑 鳥獣戯画のコラムや、美術館を翔る藤田嗣治(どの美術館にも作品がある⁇) 2024/03/09
てくてく
7
紹介されている12の博物館・美術館の半分しか行ったことがないので、残りのこだわりのあるところ、特に群馬県立館林美術館と青森県立美術館にも行ってみようと思った。対談形式でまとめているのでそこがちょっと冗長に感じるとこはあった。2024/03/06
-
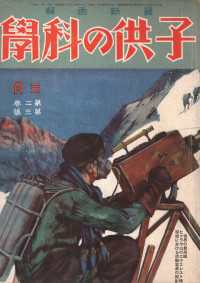
- 電子書籍
- 子供の科学1925年3月号【電子復刻版】