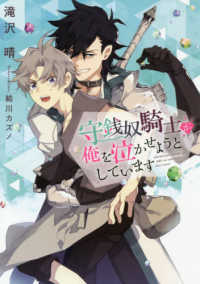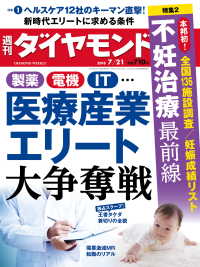内容説明
人間の条件と可能性を大胆に更新する人類学者インゴルド。ジャンルを越えて共感を呼んだ『ラインズ』につづく待望の邦訳。“線”から“つくること”へ!
目次
第1章 内側から知ること
第2章 生命の素材
第3章 握斧をつくること
第4章 家を建てること
第5章 明視の時計職人
第6章 円形のマウンドと大地・空
第7章 流れる身体
第8章 手は語る
第9章 線を描く
著者等紹介
インゴルド,ティム[インゴルド,ティム] [Ingold,Tim]
1948年英国バークシャー州レディング生まれ。社会人類学者、アバディーン大学教授。トナカイの狩猟や飼育をめぐるフィンランド北東部のサーミ人の社会と経済の変遷についてフィールドワークを行う
金子遊[カネコユウ]
1974年生まれ。映像作家、批評家、民族学研究。慶應義塾大学非常勤講師
水野友美子[ミズノユミコ]
1983年生まれ。関心領域は社会的過程としてのアート
小林耕二[コバヤシコウジ]
1969年生まれ。東欧文化研究(美学)。総社土曜大学主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件