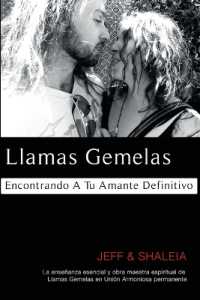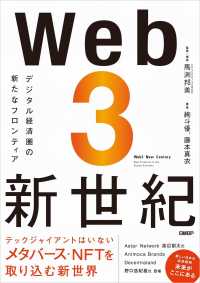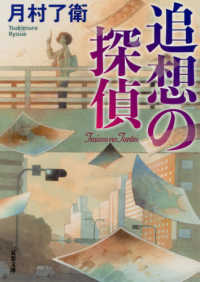内容説明
この2年半で何が変わったのか?2013年11月シンポジウム「未来に可能性はあるか?3.11以降の社会構想」にて交わされた緊急提言を書籍化!
目次
インタビュー 捨ててきたものの中に希望がある
シンポジウム・講演(不可能なことは何能である;憲法の未来;死者・デモクラシー・無縁;成熟社会の経済のあり方)
シンポジウム・討議 未来に可能性はある
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
maylucky
2
原発や安保法制など、デモがあれほど盛んな割には結局選挙で投票率が低く、自民公明が圧勝する。若者の投票率も予想通り低い。何故なのかと常々疑問に思っていたが、「日本人は意思決定することが苦手」という一文に納得した。お金を使うことも意思決定、つまり損する可能性もある行為だけに、皆使わずにため込んでしまうのだね。原発に反対でも、じゃああなた責任もって反対できますか?と問われると、「いや、まあ、じゃあ今のままで。」との答えになってしまう。暗い気分になるが、著者4人のような新進気鋭の論客が活躍する日本に期待したい。2016/10/29
マウンテンゴリラ
1
不可能性の時代における可能性の追求。これが、本書のタイトルである「ぼくらは未来にどうこたえるか」ということへの社会学的課題ということだろうか。それを、憲法、民主主義、経済の視点から説き起こし、社会全体の可能性を探ろうとするものであろうか。本書における各論者の見解も、必ずしも統一的なものではなく、未来に向けての新たな可能性が見えてきたとまでは言い難いかもしれない。しかし、冒頭の基調講演で言われるように、現在の日本社会が沈みゆく船の状態にあることは、パネリスト全員、そして、多くの日本人が憂えている。→(2) 2017/06/10
Hoido
1
2013年の講演記録だが、そのままと言うかほとんど予言通りになってしまっている。私たち一人ひとりが「沈みゆく船からどう乗り移るか」について考えるべき時に、誰も何も考えようとはしない。 乗り移る船は目に見えるところにあるのだが、誰もそれを見ないようにしている。 救命艇を探す、若しくは自作する。リスクを承知で飛び込んで泳いで渡る。ほかにも色んな手段はあるのだが、誰もそれを実行に移そうとはしない。 本書にはそんな人々に勇気を与えるアイデアが書かれている。なので泳げない人にこそ是非読んで欲しい一冊。2016/11/20
Tatsuo Mizouchi
0
☆☆☆ 死者へのデモクラシー。死者の思いと順接しつつ、逆接する。インクルージョンとエクスクルージョンのバランス。ふたつともとても誤解を招く表現だけど、、、2017/10/02