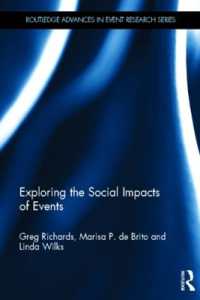内容説明
藝大で福祉?“認知症を演劇で擬似体験”“「死にたい人の相談にのる」という芸術活動”“西成のおばちゃんと立ち上げるファッションブランド”etc.東京藝術大学生と社会人がともに学んだ「アート×福祉」プロジェクトの記録。
目次
なぜ「アート×福祉」?―アートの特性が社会を変える(日比野克彦)
講義編(「助けて」といえる社会へ―ホームレス支援と「子ども・家族marugotoプロジェクト」(奥田知志)
「風テラス」という試み―セックスワーカーの法律相談(浦〓寛泰)
ダイバーシティと「表現未満、」―重度知的障害者と家族の自立(久保田翠)
鬱から始まるアート―躁鬱研究家と「いのっちの電話」(坂口恭平)
誰もが誰かのALLYになれる―多様な性のあり方とフェアな社会(松岡宗嗣) ほか)
実践編(対談 福祉と建築が向き合う、答えなきもの(金野千恵×飯田大輔)
取材記事 普通って何だろう?―「見た目問題」を超えて(取材先 石田祐貴)
取材記事 日常というギフト―地域の「信頼」というセキュリティ(取材先 ミノワホーム)
取材記事 誰かのミカタ地図―孤立したひとの居場所をつくる(取材先 香取CCC)
論考 他者について想像する力、変わろうとする力(田中一平) ほか)
-

- 電子書籍
- 守護神は攻め上手【タテヨミ】第76話 …