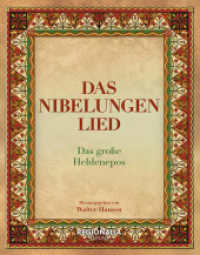内容説明
われわれが用いる言葉のうち、およそ修辞的でない言葉など存在しない。美学的崇高の背後にある修辞学的崇高の系譜を、ロンギノス『崇高論』からボワローらによる変奏を経て、ドゥギー、ラクー=ラバルト、ド・マンらによるこんにちの議論までを渉猟しつつ炙り出す。古代から現代へと通底する、言語一般に潜む根源的なパラドクスに迫る力作。
目次
第1部 『崇高論』と古代(真理を媒介する技術―「ピュシス」と「テクネー」;情念に媒介されるイメージ―「パンタシアー」と「パトス」;瞬間と永遠を媒介するもの―「カイロス」と「アイオーン」)
第2部 変奏される『崇高論』―近代におけるロンギノス(崇高論の「発明」―ボワロー『崇高論』翻訳と新旧論争;言葉と情念―バーク『崇高と美の観念の起源』と言語の使命;「美学的崇高」の裏箔―カント『判断力批判』における修辞学)
第3部 崇高なるパラドクス―二〇世紀における「崇高」の脱構築(放物線状の超越―ミシェル・ドゥギーと「崇高」の詩学;光のフィギュール―フィリップ・ラクー=ラバルトと誇張の哲学;読むことの破綻―ポール・ド・マンにおける「崇高」と「アイロニー」)
著者等紹介
星野太[ホシノフトシ]
1983年生まれ。専攻は美学、表象文化論。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。現在、金沢美術工芸大学講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たか
5
難しい…2017/06/12
たぬき
2
研究書を読んで書いたような本だな。
my
2
言語に対して誠実な本だった。美学において自明のように扱われる「崇高」の概念を問い直し、それが修辞学の文脈にいかように位置付けられるかを精緻に問い直す。著者は崇高概念に対し一定の距離を保ち、誠実に文献を追ってゆく。星野のその立場に添いながら読むことで、読み手も崇高を相対化しつつ、単に「美」の対概念として受け取っていた崇高を様々な角度から理解し直すことができる。抑制の効いた精緻な語り口は崇高論につきもののパッショネイトな難解さとは一線を画していると感じた。良書。2018/05/22
yu-onore
1
テクネ―によりピュシスの手綱が握られピュシスが明らかになりながらもテクネ―が隠れ、パトスによる情念の共振がイメージを伝え、他なる時代を引用しながら通時性へと到達するような技術として描かれた修辞学的崇高と、その現在の系譜。崇高を上昇として捉えたドゥギーと、日常的言語であっても、アイロニーにおけるパフォーマティブな次元での決定不可能性が決裂を生みうると考えるド・マンが興味深い。2021/08/02


![シンプル卓上カレンダー [カラー/A7ヨコ]【T2】 〈2026年〉 永岡書店の卓上カレンダー](../images/goods/ar2/web/imgdata2/45226/452264552X.jpg)