内容説明
時に小さく時に大きく「社会」の範囲を見積ることで「偏り」を隠蔽に維持しようとする権力装置。矮小化された「障害の社会モデル」理解をアップデートすることによって、「マジョリティ性の壁」を見定め突き崩すための思考の在り方=新たなモードを提示する。
目次
序章 「社会」の語り口を再考する
第1部 「社会モデル」でみる現在(当事者研究と「社会モデル」の近くて遠い関係;「心のバリアフリー」は毒か薬か;性の権力は障害者の味方か?)
第2部 合理的配慮と社会モデル(合理的配慮は「社会モデル」を保証するか;社会的な問題としての「言えなさ」;変えられる「社会」・変えたくない「社会」)
終章 「社会モデル」を使いこなす
著者等紹介
飯野由里子[イイノユリコ]
1973年生まれ。城西国際大学大学院人文科学研究科博士後期課程修了。博士(比較文化)。現在、東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター教員
星加良司[ホシカリョウジ]
1975年生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士後期課程修了。博士(社会学)。現在、東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター教員
西倉実季[ニシクラミキ]
1976年生まれ。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程修了。博士(社会科学)。現在、東京理科大学教養教育研究院教員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
awe
9
障害の社会モデルは、社会運動においてのみならず、現在の行政においても合理的配慮の文脈等において取り入れられており、一見良い方向に社会が進んでいるように思われる。しかし、往々にして社会モデルの理解が誤っている、或いは不足しているがために、様々な問題が生じつつある。そうした問題意識から3人の社会学者らが議論を展開する。◆障害の社会モデルを3つのレベルに分節化するという前提が共有されてから各自の論考が展開されるのだが、これが非常に分かり易い。(1)発生メカニズムの社会性(2)解消手段の社会性(3)解消責任の2023/09/20
いとう・しんご
8
「プシコ ナウティカ」きっかけ。新自由主義的言説に介入する必要P192に言及するわりには、全体に微温的。合理的配慮という言い方に落着させた経団連や御用組合、御用学者を、社会的マジョリティと呼ぶことで隠蔽しているのではないか。2025/06/18
やっぱ犬が好き♡
5
「障害の社会モデル」には本来、「障害者を不利な立場に追いやり、非障害者の特権を生み出し温存する権力構造」についての視点や問題意識が中核としてあった。本書はこの「障害の発生メカニズムの社会性」を軽視すること(または歪曲すること)で、理論実践面で障害者にもたらす負の影響について、具体的な言説や合理的配慮の事例の問題点をあげ考察している。 自分の社会モデル理解がずいぶん半端だったし、諸々の言説の問題点(とくに当事者研究)について気づけず、本書の指摘を読むまでナイーブに受け取っていたのは結構恥ずかしい話だ・・・2022/08/07
いとう
4
障害者配慮・支援の根底には個人モデルに基づく論理が潜んでいることが少なくない。障害発生の認識論に無自覚なまま、合理的配慮と称してバリアをフラットにしても、対話によって建設されるものは、個人モデルに滑り落ちる危険性を孕む。 自らの特権性(加害性)に気づかないままでいたいマジョリティ、個人モデルの密輸入、個人モデル的な解決を選好する臨床心理学。 ・・・再読する2024/09/10
バーニング
3
重要な本なので一章ずつゆっくりと読んだ。「社会モデル」について考える前に私たちの生きる「社会」の構造の理解が重要なのに、熊谷晋一郎や綾屋紗月のような当事者でもあり研究者でもある人たちですらその視点を十分に持たないことを痛烈に批判している。特に熊谷は一般にも知られており、メディアにも頻繁に登場するが彼ですら社会モデルについての理解が不十分であるという一連の指摘を読んでいると、「メディアで取り上げられる障害者」の像がいかに偏っているのかも強く感じる。さらに個別では3章の障害者の性に関する議論が読み応えあり。2025/04/03
-
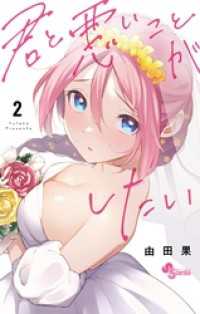
- 電子書籍
- 君と悪いことがしたい(2) 少年サンデ…




