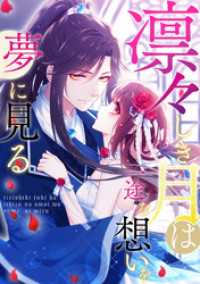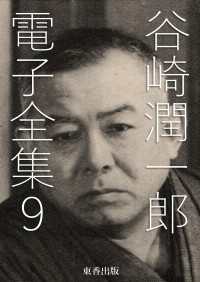内容説明
コルビエール、ランボー、マラルメらを世に知らしめ、同時代人の蒙を開き、次代に甚大な影響をもたらした詩人ヴェルレーヌによる画期的評論。
目次
緒言 掲載の肖像について
1 トリスタン・コルビエール
2 アルチュール・ランボー
3 ステファヌ・マラルメ
4 マルスリーヌ・デボルド=ヴァルモール
5 ヴィリエ・ド・リラダン
6 哀れなルリアン
著者等紹介
ヴェルレーヌ,ポール[ヴェルレーヌ,ポール] [Verlaine,Paul]
1844‐96。フランスの詩人。メッスに生まれ、パリに暮らした。合同詩集『現代パルナス』でデビュー、その後三冊の詩集を刊行するが、パリ・コミューンへの傾倒、ランボーとの関係により詩壇で孤立。1872年妻子を捨ててパリを出奔。翌年ブリュッセルでランボーを拳銃で撃ち有罪判決に。獄中でカトリックの教えに立ち戻り、釈放後はイギリスで教師をつとめたが、帰国後は再び飲酒と漁色に溺れて身を持ち崩す。貧窮の一方で名声は高まり、「デカダンス」の首領として次代を担う若手文学者の尊敬を集めた
倉方健作[クラカタケンサク]
1975年東京生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程退学後、同研究科で博士号(文学)取得。現在、九州大学言語文化研究院准教授。専門はヴェルレーヌを中心とする近代詩(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たち屋たちや
17
少年期から青年期を、みるために 自分を省みることもしなかったのは 一種の狂いがあったのか。 憂いのほうが大きかった気がしなくもないですが。2020/07/10
qoop
8
執筆当時、正当に評価されたとは云い難い詩人たちを俎上に上げて称揚し、彼らの声望を高めようとした著者。人格・行状批判に基づき詩作を黙殺されていた著者にとって、彼らの中に自身を二重写しに見たのだろうし、何より表現したかったのは自分のこと(影響力や視点の確かさ)だろうな、と思わなくもない。評論ではなく感想だというのも、何というかそぐう。タイトルの名付けセンスが素晴らしいのは言うまでもないが、こんな題名つけられたから読まざるを得ないな、と。2021/12/24
渡邊利道
6
すごく有名な本で、はじめて読んだが状況依存性が高く、解説が一番面白かったかも。ヴェルレーヌってダメなやつだなあ的な。変則的なアンソロジーとして読むのがいまとなってはよいのかもしれない。やっぱマラルメいいなあとか言ってみてもしかたがない感じもしないではない。2021/08/03