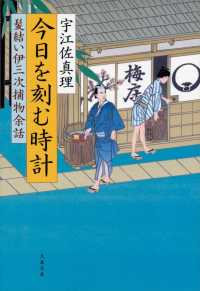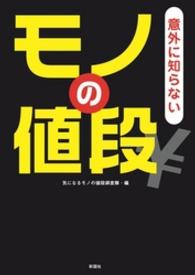目次
日本家屋、雨と多湿を凌ぐ知恵
桧皮葺・柿葺
瓦葺
「雨」と土地の生態文化
描かれた雨と見えない雨
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mura_ユル活動
95
「住まいは夏を旨とすべし」(吉田兼好・徒然草)。多くは、夏期高温多湿の日本。長い間、特に雨に湿気に耐えられるように考えられてきた住まいの仕組み。この雨の続く時期に読んでみた。写真多くわかりやすい。雨戸の敷居のディテールは、一際、関心を持って拝読。図書館の「雨」特集で置かれていた本。2019/06/09
けんとまん1007
20
日本は瑞穂の国。水、雨の国でもあると思う。そんな雨と、いかにしてつきあうかと、先祖の時代から考え、今日に至っている。そんな歴史や文化・伝統という言葉を思い出した。人は、生命は水がないと成り立たないもの。ある意味、恵まれた環境にあるともいえる。見ていて、新たな発見がたくさんある1冊。2016/05/16
バニラ風味
19
表紙のデザインからして素敵だな、と思いました。今は洋風建築が多く、日本家屋は少なくなってしまいましたが、屋根の茅葺や瓦、縁側や庇などの知恵と工夫には感心させられます。縄文時代からの家の造りの移り変わりの歴史や、洋風建築との決定的な違いなど、とても幅広い視野で書かれています。また、最後に雨をテーマにした、東海道五十三次などの日本画が掲載されいるのも興味深かったです。カラー写真豊富で、ページをめくって見るだけでも、勉強になります。2016/05/04
あろはま子
4
日本古来の美しい古民家が少なくなっていることがとてもさみしく感じた。 かやぶき屋根は地域のコミュニティにおけるイベントだったはずで、そこからも日本人がどのように変化していったか感じる。古民家はこれからの観光にも素晴らしいアイテムになると思うのでまた復活してほしいな、日本の住まいの知恵。2015/01/07
きのたん
1
中に一軒、床全面に竹が渡してあるだけの家があって、どうやって歩くんだろうと思った。健康青竹踏みどころじゃなくて、小石が敷き詰められた地面以上の衝撃がありそう。しとみ戸がオシャレで良い。狭い路地のお店なんかに向いてる。開店時は日除けとして、閉店後はシャッターとして。2017/12/19