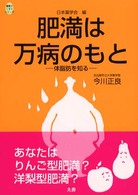内容説明
ソ連のずさんな住宅政策の遺産を引きずるモスクワ。個人宅を訪ねて住にまつわる市民の悲喜こもごもをレポート。
目次
第1章 若者たちの住まい
第2章 家族の住まい―「スターリンカ」の現在
第3章 家族の住まい―「フルシチョフカ」の現在
第4章 1970年代以降の住宅
第5章 新築マンションの悲喜こもごも
第6章 ダーチャの現在
著者等紹介
道上真有[ミチガミマユ]
1974年、和歌山県生まれ。学歴、大阪市立大学大学院経済学研究科後期博士課程修了、博士(経済学)。職歴、日本学術振興会特別研究員(PD)、(財)日本国際問題研究所研究員を経て、新潟大学経済学部准教授。専門、ロシア経済論、比較経済体制論、ロシア住宅市場・住宅政策(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
D21 レム
19
「テレビでロシア語」でサンクトペテルブルグのロシア人の集合住宅や、郊外の別荘ダーチャが出てきて、興味を持ったので読んだ。ソ連時代は住宅は国から支給されるものだったらしい。家族ごとにちょうどいい住宅を割り当てることが難しかったらしい。あと、政治的によくない動きを国民がしないように…とか、いろんな思惑が住宅にはあったようだ。ダーチャも、ソ連時代は2階建ては禁止で、夏だけの住居なので暖房も取り付けてはいけなかったらしい。また、ダーチャは行くのが不便で、生活も水を汲んできて生活排水はためておいて捨てに行くなど大変2017/01/27
O. M.
2
実際の一般市民宅の実地調査・インタビューに基づく、現代モスクワの住宅事情の調査報告。ご存知の通り、モスクワの住宅は、かつてソ連時代には政府によって供給されてきた訳ですが、スターリン~フルシチョフ~ブレジネフ以降と、時の権力者の政策によって世代ごとの住宅の特徴が異なっているそうだ。また、住宅が私有財産化された後の現在ロシアにあっても、ロシア人の多くは、住宅はいまだ政府が整備すべき基礎的インフラと考えているという本書の考察は興味深かった。マニアックなテーマだが、素人の私にも分かり易い解説で勉強になった。2014/03/30
晴天
1
都市と住宅問題とは切っても切り離せないが、ヨーロッパ最大の人口を誇る過密都市モスクワではその深刻さは著しく、また、ソ連時代の1戸に数家族を押し込むコルナルカ、極限まで生産性を追求したアパート群フルシチョフカなどの独特の様相は今に至るも精神に、あるいは不動産の形で根を下ろしている。また住宅市場の誕生と共に新築マンションも建設されているがその価格は高騰している。そして市場化しても尚、住宅は政府が手当するものという意識も残る。こうした住宅の様相は断片的に伝え聞くが、一冊の本として描かれるのは新鮮である。2021/07/09
narmo
1
ソ連時代に住宅ローンのようなものがある、と聞いたので、そのことを知りたくて手に取った一冊。私が求めていた「協同組合方式のアパート建設」については何度か言及はあったものの、その内容については書かれていなくて残念でした。その点以外は、とても面白かった!国の家族観が住宅建設に多大な、かつ、具体的な影響を与えることがあるなんて。一瞬、共産主義もありなのかも?と気持ちを震わせる瞬間もあったりして(いや、やっぱ無理ーと突っ込みつつ(笑))、楽しみながら読了しました。2017/08/09
-
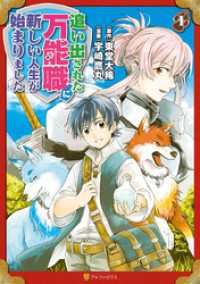
- 電子書籍
- 追い出された万能職に新しい人生が始まり…