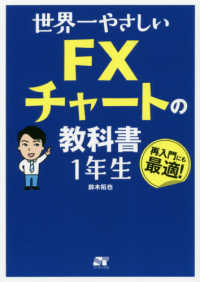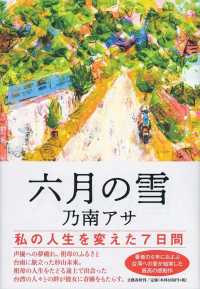出版社内容情報
低地遺跡から古墳時代の始まりを探る
古墳時代の始まりに当たって、関東地方では様々な変革が行われた。特に集落では、弥生時代まで全く見られなかった周溝持建物が建物形式として採用され、関東平野の主要な低地部で、それまでとは全く異なる建物構成の大規模集落が出現した。しかし、様々な経緯から長らくそれらは方形周溝墓として誤認され、ほとんど様相が明らかでなかった。本書は関東地方の周溝持建物による集落を網羅的に検討し、具体的な様相をはじめて示したものである。更にその成果から、伝統的な台地上の竪穴建物集落、低地の竪穴建物集落との間で形成されたシステムの存在を明らかし、古墳時代開始期の新たな社会モデルが構築されている。古墳時代の始まりを新視角から検討した研究者必携の書である。(早稲田大学博士論文に加筆刊行)
「発刊によせて(早稲田大学名誉教授 岡内三眞)」より抜粋
本書は、文化財の調査を実地に担当し、長年にわたって考古学の研究と思索を続けてきた福田聖氏の労作です。
(中 略)
周溝持建物は、古墳時代前期になると関東地方の低地に広く分布すると指摘します。そして低地では竪穴建物が土器製作や玉作りなどに使われ、周溝持建物は遺物や遺構からみて外来系要素を受け入れる役割をそなえているとみています。さらに台地上に位置する竪穴建物を加えた三者が、それぞれの機能を補完しあって集落を形成しながら、古墳時代社会へ移行していったと捉えます。
関東地方は地域社会の分節集団の力が強く、首長は階層的格差の少ない「関東型一般集落」を構成し、地域経営が行われたとみて、関東における古墳時代開始の特質を明らかにしているのです。
土器製作や玉作りなどの変革期と建物の導入時期や構成要素を検討し、従来には見られなかった新たな社会像を描きだすことに成功しています。
新出資料と斬新な視点にたって書かれた本書を、一人でも多くの方々に読んでいただき、調査や研究に活用されることを祈って止みません。
【目次】
第1章 はじめに
第1節 古墳時代研究の新たな視点と研究方法
第2節 方形周溝墓と周溝持建物認定の基準
第2章 荒川低地南部の低地遺跡
第1節 旧入間川流域
第2節 三ツ和遺跡
第3節 鍛冶谷・新田口遺跡
第3章 荒川低地北部の低地遺跡
第1節 鴨川・入間川・市野川流域
第2節 元宿遺跡
第3節 荒川低地北端・笠原低地・熊谷低地
第4章 妻沼低地・加須低地の低地遺跡
第1節 妻沼低地南部
第2節 妻沼低地西部・志戸川扇状地・女堀川扇状地
第3節 加須低地
第5章 東京低地の低地遺跡
第1節 東京低地東部
第2節 旧入間川右岸
第3節 豊島馬場遺跡
第6章 周溝の性格と機能
第1節 方形周溝墓と「周溝」の覆土・出土状況(1)
第2節 方形周溝墓と「周溝」の覆土・出土状況(2)
第3節 関東地方における「周溝」研究の経緯と課題
第4節 「周溝」と「周溝持建物」の様相
第5節 周溝区画内の建物形式
第6節 周溝持壁立式平地建物の性格
第7節 周溝持建物を建てた人々
第8節 建物跡ではない「周溝」
第9節 小 結
第7章 低地遺跡から見た古墳時代への変革
第1節 周溝持建物の地域差と関東地方への導入の意義
第2節 結 論