1 ~ 1件/全1件
-

- 電子書籍
- TS衛生兵さんの戦場日記【ノベル分冊版…
-
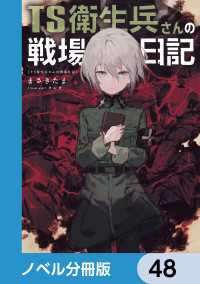
- 電子書籍
- TS衛生兵さんの戦場日記【ノベル分冊版…
-
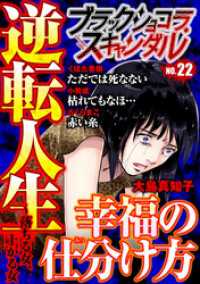
- 電子書籍
- ブラックショコラスキャンダルno.22…
-

- 和書
- まちの図書館でしらべる
-

- 和書
- 講義経営学総論



