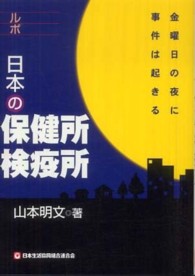目次
曇りガラスが晴れるとき―“なぜ?”と聞くのは間違いの始まり
第1部 メタファシリテーションの成立(「なぜ?」と聞かない対人援助コミュニケーション手法;思い込み質問の迷路から「簡単な問い」へ;簡単な質問の先の壁;メタファシリテーションの成立)
第2部 メタファシリテーションを囲む「枠」(コンテクストが見えてきた;「コミュニティー」に至る道;マクロとミクロの間;国際協力のコンテクスト=近代化に伴う貧困現象の発生)
第3部 メタファシリテーションの実践(メタファシリテーションの技法解説;メタファシリテーションのプロジェクトへの応用)
結論に代えて
著者等紹介
和田信明[ワダノブアキ]
1950年東京生まれ。ストラスブール大学人文学部中退。高山市の飛騨国際工芸学園教員などを経て、1993年にソムニードの前身の「サンガムの会」を設立。南インドで多くのプロジェクトを現在まで手がける。2002年にネパールでも活動を開始、2007年からは森林保全プロジェクトを実施中。併せて、旧国際協力銀行の委託による森林共同管理関連の調査をインド全域で行ったり、国際協力機構(JICA)の技術協力プロジェクトの短期専門家としてインドネシアを頻繁に訪れ、コミュニティー・ファシリテーター育成研修を行ったりと、ODAプロジェクトにも密接に関わる
中田豊一[ナカタトヨカズ]
1956年愛媛県生まれ。東京大学文学部卒。アジア学院農場ボランティアなどを経て、1986‐89年、シャプラニール=市民による海外協力の会ダッカ駐在員としてバングラデシュで活動。1995年1月、兵庫県尼崎市で阪神淡路大震災に遭遇、直後より阪神大震災地元NGO救援連絡会議事務局長代行として救援活動に従事。同年5月から1998年3月まで(社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン事務局長。1998年、参加型開発研究所開設。以後、フリーランスの国際協力コンサルタントとして活動(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
香菜子(かなこ・Kanako)
アナクマ
きいち
ちぃ
-
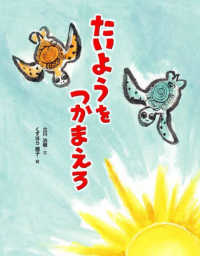
- 和書
- たいようをつかまえろ