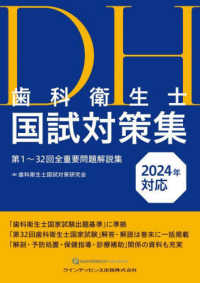出版社内容情報
1910年、17匹のマングースがインドから沖縄に上陸した。サトウキビを食い荒らすノネズミと猛毒のハブを駆除するためで、画期的な方法と期待された。マングースたちは環境の変化や戦火を乗り越え、たくましく子孫を増やしていった。しかし、夜行性のハブ退治に役立っていないうえに沖縄固有の生物を捕食していた。
1981年、北部のやんばる地域でヤンバルクイナが“発見”され国の天然記念物に指定されると、やんばるの自然環境や保護が注目され、同時にマングースは“外来生物”として駆除の対象となった。
人間が自然を“守る”とは? “外来生物”とは?……。
さまざまなことを考えるきっかけとなる1冊。
著者等紹介
ヒサクニヒコ[ヒサクニヒコ]
ヒトコマ漫画家、イラストレーター、乗り物愛好家、恐竜研究家。1944年、東京生まれ。1951年より横浜在住。1966年慶應義塾大学法学部卒業。1972年文春漫画賞受賞(マンガ太平洋戦史)。2018年産経児童図書文化賞(世界恐竜発見地図)。世界や日本の歴史、恐竜・野生動物などの森羅万象を、世界各地へ赴き見て歩いてきた。恐竜の化石や野生動物に触れたくて、日本や海外の博物館や発掘現場へも足を運んでいる。特にアフリカのサバンナへは20回以上も訪れている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
瑪瑙(サードニックス)
32
無知とは本当に恐ろしい。ハブ退治の為に連れてこられた17匹のマングース。一生懸命生き延びて子孫を残してきたけれども、ハブではなく、ヤンバルにしか生息しない希少種を食べてしまっていた。慌てて駆除にかかる人間。勝手に連れてきて放し、今度は人間の都合で駆除する。マングースは被害者だ。今後、外来種を勝手に連れてきて勝手に放す事のないように、十分に知識を蓄え、気をつけてほしいと思う。2025/10/26
どあら
25
図書館で借りて読了。生態系のことを考えずにマングースを放したのは人間だし、厄介者と言って外来種を駆除するのも人間…。彼らから見たら一番怖い生き物でしょうね…😔2025/10/11
遠い日
8
明治時代も終わりの頃、1910年に沖縄の那覇付近で放たれた17匹のマングース。外来生物の生態系への影響などまだ知られていない頃なので仕方のないことといえばそうなのですが、ハブを捕えるという漫然とした知識で、沖縄の生態系を壊す未来が待っているとも知らずに行った施作。結果はあまりにもひどいものでした。マングースがどういう動物なのかも知らずに、イメージだけでしたことが長きに渡り現地の混乱を引き起こしました。外来生物の問題が明らかになった今、やりきれないもやもやが残ります。2025/06/22
ジャスミン
5
小3娘読み聞かせ。外来生物の問題が子どもにも分かりやすく描かれている。沖縄や日本の生き物がたくさん紹介されていて、図鑑のようにも楽しめます。安易に生き物を持ち込むのは、お互い幸せになれないということが、よくわかります。2025/06/28
飴
4
よかったです。ボリュームが絵本で、でも 読みものとしてもしっかりと楽しめて、外来生物といわれる連れてこられた生きものの生態を丁寧に。こういう本が、中学年の課題図書だといいと思いました。わかりやすい文章、生きものいっぱい。2025/06/11
-

- 和書
- モダン・ゴルフ