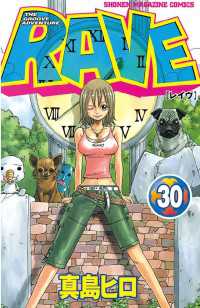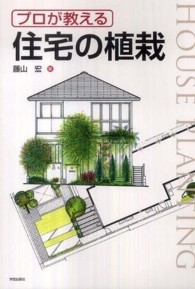出版社内容情報
40年間、太平洋でウナギを追い続けたウナギ博士。その研究の集大成!世界のウナギの7割を食べる日本人なら読んでおくべき一冊!
はじめに
第1章 なぜ、動物は旅に出るのか
――ヒトも魚も「脱出」する
動物の移動は目的のない「旅」
通し回遊の三つのパターン
アユは水温が上がると「脱出」する
「育ち」によって最適な個体間距離が違う
琵琶湖の大アユ小アユの不思議
中途半端な個体が担う大事な役割
動因上昇時のホルモン
人類のアフリカ脱出はどのように起きたか
第2章 ウナギの進化論
――深海魚から回遊魚へ、二億二〇〇〇万年の歴史
パラオの海底洞窟にいたウナギの祖先
ウナギ全種を世界中から集めよ
新種アンギラ・ルゾネンシス
マハカム川を遡上した《イブ》
なぜ、海から川へ向かったか
成育場は広く、繁殖場は狭い
耳石の分析で素性がわかる
親ウナギの大部分は海洋残留型だった
第3章 ネガティブ・データの大切さ
――グリッドサーベイと耳石の研究
大西洋の産卵場を発見したシュミット博士
「船の墓場」サルガッソ海
ヨーロッパウナギとアメリカウナギは交雑するのか
ニホンウナギの産卵場を探せ
グリッドサーベイをしよう
耳石の日周輪解析
二四時間三交代の船上作業
レプトセファルスはだんだん小さくなった
耳石から産卵時期と場所が推定できた
第4章 海山に「怪しい雲」を追う
──三つの仮説と検証の一四年
調査航海の時期を夏に変更した
塩分フロントの南で九五八匹――「塩分フロント仮説」
新月の晩に合同結婚式を挙げている――「新月仮説」
そこに三つの山がある──「海山仮説」
空白の一四年間――なぜ、卵の採集が困難か
潜水艇ヤーゴで海山域に潜る
「怪しい雲」を追え
科学者の使うべき言葉
ウナギそっくりの魚影が映った
第5章 ハングリードッグ作戦
──なぜ、親ウナギは塩分フロントを求めるか
トウキョウ・イール
二つの新兵器
動く塩分フロント
産卵場に急行せよ
世界初、天然のプレレプトセファルスを採集!
二〇〇五年の産卵場はスルガ海山近傍
産卵場の水深はどれくらいか
銀ウナギの日周鉛直移動
海の一次生産は表層一〇〇メートル
故郷の「匂い」はマリンスノー
第6章 ウナギ艦隊、出動ス!
──世界初の天然卵採集、親ウナギ捕獲
「ウナギ産卵場における親魚の捕獲調査」
開洋丸、親ウナギの捕獲に成功!
二種のウナギの同所的産卵
ウナギ艦隊、海山域に展開
丸二昼夜の興奮
温度躍層の絶妙な仕組み
産卵前の親ウナギを捕獲
重要なのは塩分フロントの位置だ
シラスウナギ不漁の原因は何か
二〇一二年は死滅回遊が少ない
第7章 ウナギ資源保全のために何をすべきか
──回遊の多様性と完全養殖実用化のポイント
養殖のネックはレプトセファルスの餌
なぜ、大西洋の二種は産卵場がわからないか
何のために幼生期の比重が変化するか
日周鉛直運動のメカニズム
「貿易風仮説」
最も変態の遅いグループが利根川を遡行する
河口がウナギの難所になっている
幻の「アオウナギ」の正体
三年間の大不良の波は一〇年後に再来する
おわりに
【著者紹介】
1948年岡山県生まれ。農学博士。専門は海洋生物学・魚類生態学。1971年東京大学農学部水産学科を卒業後、1973年東京大学大学院農学研究科博士課程に進学、1974年東京大学海洋研究所に助教として着任。1986年の准教授就任を経て、1994年に教授に就任。独自の「海山仮説」「新月仮説」「塩分フロント仮説」に基づき、世界で初めて天然ウナギの卵を北太平洋・西マリアナ海嶺南端部の海山域で採集することに成功。ウナギの産卵地点をピンポイントで特定し、2400年におよぶウナギ産卵生態の謎を解明した。しばしば「世界的ウナギ博士」と称される。その研究功績から、1986年日本水産学会賞(奨励賞)、2006年日本水産学会賞、2007年日本農学賞・読売農学賞、2012年日本学士院エディンバラ公賞など多数の賞を受賞している。
内容説明
世界初!マリアナ海嶺で天然卵の採集に成功!アリストテレスから2400年、ウナギ誕生の『謎』が遂に解明される―。知的興奮を得られる上質のサイエンスアドベンチャー。
目次
第1章 なぜ、動物は旅に出るのか―ヒトも魚も「脱出」する
第2章 ウナギの進化論―深海魚から回遊魚へ、二億二〇〇〇万年の歴史
第3章 ネガティブ・データの大切さ―グリッドサーベイと耳石の研究
第4章 海山に「怪しい雲」を追う―三つの仮説と検証の一四年
第5章 ハングリードッグ作戦―なぜ、親ウナギは塩分フロントを求めるか
第6章 ウナギ艦隊、出動ス!―世界初の天然卵採集、親ウナギ捕獲
第7章 ウナギ資源保全のために何をすべきか―回遊の多様性と完全養殖実用化のポイント
著者等紹介
塚本勝巳[ツカモトカツミ]
1948年岡山県生まれ。農学博士。専門は海洋生物学・魚類生態学。1971年東京大学農学部水産学科を卒業後、1973年東京大学大学院農学研究科博士課程に進学、1974年東京大学海洋研究所に助教として着任。1986年の准教授就任を経て、1994年に教授に就任。世界で初めて天然ウナギの卵を北太平洋・西マリアナ海嶺南端部の海山域で採集することに成功。ウナギの産卵地点をピンポイントで特定し、2400年におよぶウナギの産卵生態の謎を解明した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キク
1.3manen
ポコロコ
Uzundk
cape