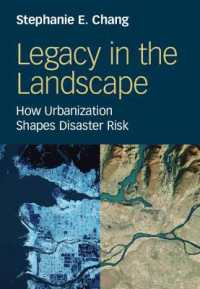目次
1 中世、迷宮への旅(継承される歌枕―御所伝来の「吉野図屏風」の情景描写をめぐって;平安期天皇主催の晴儀の歌合―その舞台装置としての洲浜台をめぐって;ヌエ考―怪鳥の声をめぐって;高野山・谷之者の原風景―図像と文献史料からの検討;『大黒舞』と清水寺の大黒天信仰―大黒天と恵比寿の原像をめぐって;善妙伝説と新羅の信仰習俗;『諸社口決』と密教的社参作法の展開)
2 能、その多面体(能とオラトリオ試論―合唱・ナレーション・宗教的機能という観点から;猿楽者による「文字」論の一端―「文字」によって謡を語る;世阿弥の稚児役者論とその時代;能「三山」と融通念仏;夜の雨枕うくほど音はこぼれて―金春禅竹の「雨」をめぐる試論;一休宗純が能に求めたもの―能「通小町」関連詩三首の検討から;観世寿夫と“江戸”;「現代思想」と能―一九七〇~八〇年代を中心に)
3 橋の会、創造への道(「橋の会」という現場;鼎談 橋の会の二十四年を振り返って;橋の会公演記録)
著者等紹介
松岡心平[マツオカシンペイ]
1954年生。1984年東京大学大学院人文科学研究科国語国文学専門課程博士課程満期退学。国文学研究資料館助手、東京大学文学部専任講師、同教養学部助教授を経て、2001年より同大学院総合文化研究科教授を務め、2020年3月に退職。一般財団法人「観世文庫」理事。専門は能・世阿弥を中心とする中世芸能。能の研究上演団体「橋の会」の運営委員を務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。