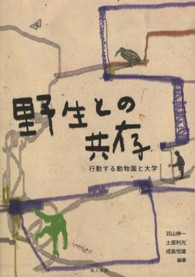内容説明
あの時代人々は何を見たのか。満洲事変後、日本は中国で戦争を拡大し、やがて米英などとの戦争に突入していった。当時の映画は、娯楽としてだけでなく、ニュース映画などをとおして一大映像メディアへと急成長していた。その影響力の大きさから、体制側は国策遂行の一環として映画に強い期待を寄せた。本書では、日本国内の映画領域と、満洲、朝鮮、台湾、中国、ドイツに関する考察を交差させて、越境的な視点から「戦時下の映画」の多様な様相を浮かび上がらせる。
目次
はじめに 「映画戦」への遠い道程
1 戦争の時代と映画(映画統制構想の展開と映画工作;“戦ふ映画館”―戦時下のオフ・スクリーン;日中戦時下の農村巡回映画の活動;教化映画か教材映画か―「動く掛図」論争以後の教育映画/映画教育の言説と実践;戦時下の映画ジャーナリズム)
2 越境する映画(初期満映について―雑誌『満洲映画』の記事から;『東遊記』論;朝鮮映画の戦時体制―第二世代朝鮮映画人と映画国策;越境する植民地劇場―日帝末期・呉泳鎮のシナリオを中心に;映画と台湾総督府の南進政策;占領下の上海映画と日本映画―文化融合と非協力;“大東亜の歌姫”李香蘭の表象性―“幻”の映画『私の鴬』再検証;ドイツの銀幕における“大東亜戦争”)
著者等紹介
岩本憲児[イワモトケンジ]
早稲田大学名誉教授。専攻=映画史、映像論
晏〓[アンニ]
日本映画大学特任教授。専攻=比較映画史、表象文化論(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- スイート リベンジ 55 FOD
-
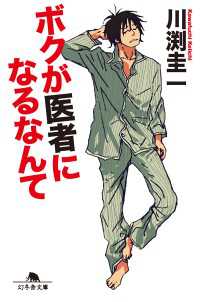
- 電子書籍
- ボクが医者になるなんて 幻冬舎文庫